教育・子育ての悩みは、どこに相談すればいいのか分からなくなったときに
教員に求められる資質能力と授業づくりの実践記事まとめ|Shirutera
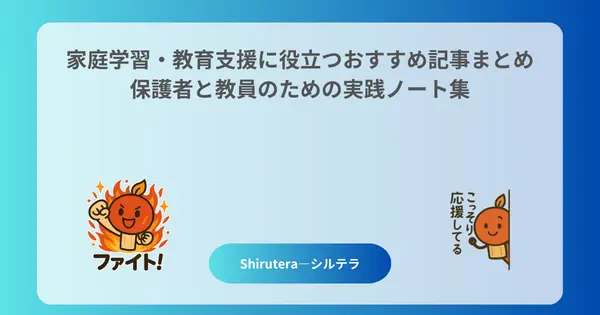
教員に求められる資質能力と、授業の専門性を高めるための実践
「教員に求められる資質能力とは何か?」──この問いに、明確な答えを持てずに悩んでいる先生は少なくありません。 ただ、最初にひとつ安心してほしいことがあります。文部科学省が重視する「学び続ける姿勢」については、 少なくともこのShirutera(シルテラ)を読んで学ぼうとしている時点で、クリアしてると言えるでしょう。
一方で悩みやすいのが、「子どもを理解する力」や「教科・授業に関する専門性」です。 制度上は示されていても、現場でどう考え、どう実践すればよいのかまでは、具体的に語られることが多くありません。 このページでは、そうした力を高めるヒントとなる実践記事や考察を中心に整理しています。
扱っている内容は、授業づくり・学級づくり・評価の捉え直し・制度と現場のズレなどさまざまですが、 共通しているのは「誰かを責めない」「自分を過度に責めない」という視点です。 漠然とした不安を抱えたまま頑張り続ける前に、 いま教員に何が求められているのかを整理する入口として、気になるテーマから読み進めてみてください。
新企画!限定1名!オンライン初任者研修
【初任者サポート】教員生活の“次の日”を支える相談枠
授業づくり・保護者対応・業務整理など、初任者の“最初のつまずき”に
ピンポイントで応えるサポート枠。
現場と教育委員会の両視点で、判断の軸を一緒に整える内容です。
はじめて読むなら、まずはこの3本から
初任者サポート、遊び×学び、体育評価──
現場で悩みやすいテーマを3本だけに絞って紹介しています。
「今すぐ知りたいこと」を最短距離で拾える入口ガイドです。
-
立ち歩き対話法とは|歩きながら話すと学びが深まる理由【教育心理×行動科学】
座り続けられない、話を聞き続けられない──。
現代の教室で起きている“集中切れ”の背景を踏まえ、
歩きながら短い対話を重ねる授業技法の核心を解説。
思考・感情・関係の3つを同時に動かす、再現性の高い実践です。 -
遊びと学びの境界線を消す──没頭が子どもを伸ばす理由
「遊び=主体的学びの原型」という視点から、没頭が学力につながるプロセスを解説。
発達心理・脳科学・実践例の3方向で2万字以上の深掘り。 -
長期休業明けの学級づくり【小学校高学年・中学校】
──クラスが「静かに動かなくなる」前に教師が整えておくべき視点
荒れていないのに、授業や学習が前に進まない──。
小学校高学年・中学校で起こりやすい「休み明け停滞」を、
やる気や指導力の問題にせず、学級構造の観点から整理します。
休業明けの準備段階で読んでおきたい、判断軸を整える入口記事です。
関連記事一覧
制度、学級経営、オンラインツール、家庭連携……
現場で使える知識を横断的にまとめたブロックです。
-
新学期、静かすぎるクラスに安心してはいけない理由
問題行動はなく、授業も一見スムーズ。 それでも後から学級が崩れていくことがあります。 新学期の「静かな安定」に潜む兆しを、教員向けに整理した解説記事です。
-
荒れていないのに学級が動かない理由──授業が進まないクラスに起きている構造の話
問題行動はないのに、なぜか授業が進まない。 その原因を「担任の指導力」や「子どものやる気」に還元せず、 学級全体の構造として整理した教員向け解説記事です。
-
『再検査は義務じゃない』って知ってた?──教員ですら知らない“学校健診”の本当の話
再検査は義務?──保護者への誤解が生まれる制度の“ズレ”を整理した記事。
-
「体育=苦手」は誰が作った?クロール25mの“評価”から考える授業
数値偏重の体育が子どもの自己肯定感をどう奪うのか、
「昨日の自分との比較」を軸に授業改善を考える記事です。 -
意味調べを“授業”にする──文脈理解・説明力・集団心理を活かす方法
「意味調べ大会」によって語彙力・説明力・学級の空気まで変わる実践記録。
-
効率的に学べるオンライン学習ツール
家庭学習で使えるオンラインツールを、習慣化の観点とセットで解説。
-
“学級目標”が形骸化するのはなぜ?──やらない目標が、ルールを壊す
目標が守られない構造と、学級文化が崩れる心理をわかりやすく整理。
-
「モンスターペアレント」の本当の定義とは──元教員が考えた線引きと危うさ
“普通の保護者”がモンペと誤解される構造を解説する導入記事。
📩 LINE登録で、教育テンプレや子育てTipsを毎週お届け!
習慣づくりややる気を引き出すための具体策が詰まっています。