教育・子育ての悩みは、どこに相談すればいいのか分からなくなったときに
『再検査は義務じゃない』って知ってた?──教員ですら知らない“学校健診”の本当の話
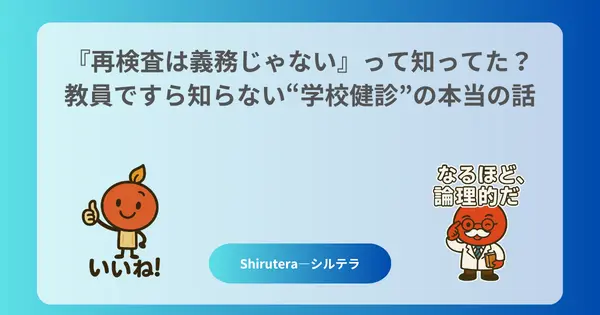
「今日、病院行かなきゃ」と焦る妻の声。
長男の耳鼻科検診の“再検査”通知を学校から受け取り、当然のように予定を調整しようとしていたその姿に、僕はふと違和感を覚えました。
彼女は現役の教員です。にもかかわらず──「絶対に行かなきゃいけない」と思い込んでいたのです。
調べてみると、実はこの“思い込み”自体が、制度への大きな誤解でした。
しかも、これは我が家だけの話ではありません。
第1章:「教員なら知ってるでしょ?」という誤解
「学校の先生なんだから、それくらい知ってるよね?」
これは、外から学校関係者を見るときによくある“期待”です。
でも、実はこの期待が、現場とのギャップを生み出している大きな要因でもあります。
たとえば「学校健診の再検査は受けなきゃいけない」という認識。
これ、教員の多くも本気でそう思っています。
なぜか?
答えはシンプルで、「ふだん制度を扱うことがないから」です。
学校健診に関する制度(学校保健安全法)を主に担っているのは、養護教諭や事務職員。
担任の教員は、再検診の通知を配布する“連絡係”になるだけで、制度の中身には触れる機会がほとんどありません。
実際、我が家の妻も現役の教員ですが──
「耳鼻科の再検査、絶対行かないといけないよね?」
と、真顔で言っていたのです。
この瞬間、僕は確信しました。
制度の知識は、現場に届いていない。
そして教員もまた、“制度の受け手”にすぎない。
第2章:「うちの話だ」と思ったnote記事との出会い
そんな出来事の数日後、たまたま出会ったのが「ただの父親ですが。」さんのnote記事でした。
タイトルは、「子どもが不登校になって、大変だったこと」。
不登校になった娘さんとの生活の中で、親として直面した“制度の壁”や“生活の変化”について赤裸々に書かれた記事で、その中にこんな一節がありました。
「健康診断や歯科・耳鼻科検診、検尿など、学校で実施される定期的な検診。
これらに参加できない場合は、別日に学校指定の病院に行かなくてはなりません。」
……これ、まさにうちの話と同じでした。
僕はすぐにコメント欄に「実は再検査って義務ではないそうです」と投稿しました。
すると著者の方から丁寧な返信があり、なんとその内容が記事に追記されたのです。
「健康診断の実施義務は、あくまで学校側にある。保護者に法的義務はない。」
経験と知識が交差して、次の誰かに届く。
このやりとりを通じて、共創だと実感しました。
第3章:制度の全体像──健康診断の“義務”は誰にあるのか?
では、改めて「学校健診の義務」は誰にあるのでしょうか?
ここで一度、法律に立ち返ってみましょう。
✅ 法的根拠:学校保健安全法
第13条:設置者の義務
「学校の設置者は、健康診断を行わなければならない」
(例:公立=市町村/私立=法人)
第14条:校長の管理責任
「校長は、健康診断を適切に実施するための管理を行う」
保護者の義務については明記されていない
→ つまり「再検査の受診」は家庭の判断でOK。
しかし実際には:
担任が「病院に行ってください」と保護者に伝える
保護者は「学校に言われた=義務」と受け取る
本人が拒否しても「どうにかしないと…」と追い詰められる
ここに“制度と現場の伝言ゲーム”が発生しています。
第4章:「知らなかった」は責められることなのか?
教員が知らないのは、怠慢ではありません。
制度が共有されない構造そのものが、問題なのです。
・養護教諭と担任のあいだに「制度的分業」がある
・事務職員と教員のあいだにも「連携の壁」がある
・教員養成のための教育課程で「学校保健安全法」を学ぶ機会が少ない
これらの要因が重なり、制度は“機能しているように見えて、共有されていない”状態になります。
もちろん、採用試験の範囲にはこれらの法律も含まれますが、全員が満点で合格するわけではありませんし、関連法令の中でもかなりニッチな法令ではあります。
しかし、教育委員会をはじめ、採用側の判断としては「全員が一定の専門知識を有する」と判断して合格判定をしているので「全員が全法令を理解している」前提で全ての物事が決まっていきます。
とても、事務的で人間味のない判断ですが、それが現実です。
だからこそ、この記事で伝えたいのは──
誰が悪いという話ではない。
でも、このままでは保護者も、教員も、制度の“命令対象”でしかなくなってしまう。
制度と私たちが“対等な関係”になるには、まず「知ること」から始める必要があるのです。
終章:「ムリなものはムリ」と言える社会へ
「ムリなものはムリです」
こう言えるかどうかは、その人にどれだけ選択肢が“事実として”届いているかにかかっています。
学校健診のように“当たり前”とされることでも、その背景には制度や法の設計がある。
それを知らずに動けば、誰かが苦しみ、誰かが我慢する構図になってしまう。
我が家では耳鼻科で耳垢を取るだけですが、健康診断を受けられなかったことを理由に半ば強制的に指定の病院で高額な検診費用を支払っている方もいると聞きます。
そして、これは教員も保護者も同じです。
自分の子どもを守るためにも。
他人の子どもを支えるためにも。
まずは知る。そこからしか変わらない。
「人を助けるには、まず正しく知ることから」──教育評論家・藤原和博
このnoteが、だれかの「ムリを言える」勇気につながりますように。
関連リンク
📌 元記事:【共創note】子どもが不登校になって、大変だったこと|ただの父親ですが。
🔗 Shirutera|教育と心理の知識メディア
💬 LINEで学びを受け取る
📩 LINE登録で、教育テンプレや子育てTipsを毎週お届け!
習慣づくりややる気を引き出すための具体策が詰まっています。