教育・子育ての悩みは、どこに相談すればいいのか分からなくなったときに
“学級目標”が形骸化するのはなぜ?──やらない目標が、ルールを壊す
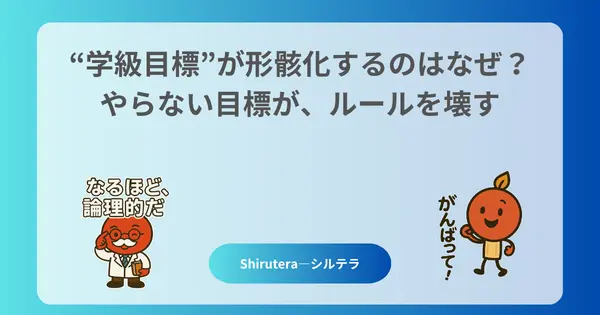
やらない約束は「守らなくていいルール」を生む──脳と集団心理のリアルな落とし穴
「思いやりのあるクラスを目指します!」
新学期に立てた学級目標。でも、1ヶ月後には誰も覚えていない。
そんな“あるある”の裏には、脳のしくみと集団心理のリアルな落とし穴がありました。
本記事では、学校目標・学年目標・学級目標のズレ、形骸化の構造、
そして「目標を掲げて守らない」ことがどれほど危険かを、
駅前の“違法駐輪”を例にわかりやすく解説しています。
さらに、目標が本当に“生きる”ための設計や運用のヒントも紹介。
「せっかくみんなで決めたのに」「書いただけで終わった」
そんな経験がある先生にこそ、読んでほしい記事です。
たとえば、駅前に「駐輪禁止」の張り紙があるのに、実際は自転車がたくさん置かれているとしたら──
それを見た人は「ここ、停めてもいいんだ」と思ってしまいますよね。
この状態が続くと、もはや“駐輪禁止”というルールは、そこに書かれていても“守らなくていいもの”になってしまう。
これは、学級目標でもまったく同じことが起きているんです。
「助け合いのあるクラスにしよう」と目標に掲げても、
教室では暴言が飛び交っていたり、廊下ですれ違っても挨拶をしない。
でも誰も注意しない。先生もスルーしている。
それを見た子どもは「この目標って、守らなくていいんだ」と、
無意識に学習していきます。
すると、その学級目標は、
“ただ掲げられているだけの紙”に変わってしまうんです。
では、なぜそんなことが起きるのでしょうか?
ひとつの理由は、「目標の重なり」にあります。
学校には、
・学校目標
・学年目標
・学級目標
の3つの“目標レイヤー”が存在しています。
たとえば──
学校目標:自ら学び、心豊かに行動する子ども
学年目標:最後までやりぬく○年生
学級目標:なかよく協力できるクラス
一見どれも素晴らしい内容ですが、
実際には「何を大事にすればいいの?」という“ズレ”が生まれます。
どの目標も立派すぎて、逆に曖昧。
そして「言葉として掲げているだけ」で、行動に落とし込まれていない。
だから、「本気で目指すもの」ではなく、
“掲げておけばいい言葉”として、受け取られてしまうんです。
これが続くとどうなるか。
子どもたちは“本当のルール”と“守らなくてもいいルール”を、
自分たちなりに分類しはじめます。
「授業中は静かにする」
→これは怒られるから守らなきゃいけない。
「思いやりを大切にする」
→別に守らなくても何も言われないから無視していい。
こうして、ルールや目標が“強制力のあるもの”かどうかで、
優先順位が決まっていきます。
そしてその空気は、知らず知らずのうちに
クラスの“文化”として根づいてしまうのです。
「思いやりを大切にする」──それが本当に機能するためには、
それを“守っている人がいる”ということを、
目に見えるかたちで感じられることが必要です。
誰かが廊下で落ちたプリントを拾っていたら、
「ありがとう」と言ってあげる。
困っている子に声をかけていたら、
「やさしいね」と先生が褒める。
そんな“小さな実践”を、教室の中で
“見える化”していくことが大切なんです。
目標は、貼り出すことではじめて生きるわけではありません。
“守られている”ことが日常の中で可視化されて、
ようやく“意味のある存在”として文化になっていく。
目標が形骸化するのは、「言葉だけ」が先行し、
それを支える行動や実感がないから。
でも逆に言えば、
毎日のちょっとした積み重ねで、“生きた目標”はつくれるんです。
📩 LINE登録で、教育テンプレや子育てTipsを毎週お届け!
習慣づくりややる気を引き出すための具体策が詰まっています。