教育・子育ての悩みは、どこに相談すればいいのか分からなくなったときに
自宅学習の最適化:効率的に学べるオンライン学習ツール
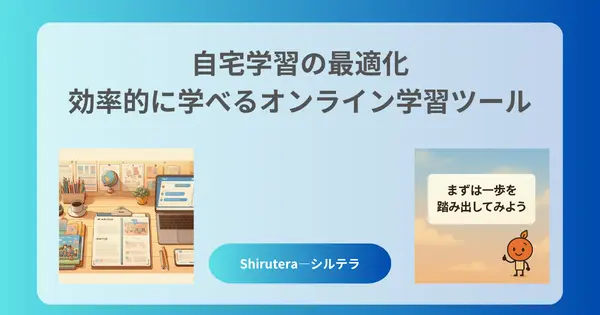
学習が続かない理由、続けられる人の違いって?
「うちの子、やる気はあるんですが、どうしても勉強が続かなくて…」
これは、僕が教員時代に何度も耳にした保護者の言葉のひとつです。
そして実際、勉強って続けるのが難しいんですよね。大人でもそうです。
でも、だからこそ今の時代、勉強を“努力”や“根性”に頼らないやり方が必要です。
そのための鍵になるのが、オンライン学習ツールの存在です。
最近では、タブレット1枚で授業を受けたり、質問したり、復習したりできる時代になりました。教室の外でも、自分のペースで学べる環境が整いつつあるんです。
でも…正直な話、
「たくさんありすぎて、どれを使ったらいいのか分からない」
「結局、続かない」
そんな声もよく聞こえてきます。
今回は、僕の独学の経験と、教育現場での実践をふまえて、「どんなツールを選び、どう使えば、“自宅学習”を効率的で楽しいものにできるのか?」について、シリーズでお届けします。
僕の独学ヒストリーと“芯のある学び”のつくり方
僕は、独学が好きです。AIを使って新しいことに挑戦するのも、趣味の幅を広げるのも、基本的には自分で調べてスタートします。
教育の世界でも、それは同じでした。「意味調べ大会」や「立ち歩き対話法」など、僕が現場で実践してきた指導法は、どれも教科書や指導書に載っていたわけではありません。
じゃあ、どこから生まれたのか?答えは、“学びに一本芯を通す”という視点からでした。
僕は教員1年目から、指導書をほとんど読んでいませんでした。自分が「面白い」と思える学びの形を追いかけました。
その結果、子どもたちにとっても楽しい授業ができるようになりました。
この「芯のある学び方」は、どんな学習にも応用できます。
オンライン学習でも、それは同じです。
“芯”を支えるツールの選び方
ここでは、僕が選ぶときに大事にしている3つのポイントをご紹介します。
①:学習のプロセスが“見える化”されていること
・学習記録がグラフやカレンダーで表示される
・AIが弱点を自動で分析・フィードバックしてくれる
②:自分のペースで進められる設計
・「毎日30分だけ」「1単元ずつ」など、習慣にしやすい構成かどうか
・部活や習い事が忙しい子にも対応できる“すき間時間”の設計
③:楽しい or 自分に合っている
・気軽に使える・デザインが好み・音声が聞き取りやすいなど感覚的な合う・合わないも判断基準になります。
おすすめツール紹介
① スタディサプリ高校・大学受験講座
・授業動画の質が高く、どの学年でも“基礎の復習”がしやすい
・料金が安く、家計に優しい(小中高:月2,178円)
② Monoxer
・AIによる反復学習で「忘れない」記憶を支援
・学習の履歴や記憶度がグラフで見える
③ デキタス
・小中学生向けで、アニメ風のキャラがナビしてくれる
・ゲーム感覚でポイントがたまり、達成感が得られる
オンラインツール×継続=最強
どんなに良い教材でも、続かなければ意味がありません。
逆に、続けさえすれば、少しずつでも成果は出ます。
だから僕は、ツール選びの最優先に「継続できるかどうか」を置いています。
毎日開きたくなるか?
サボったときの“仕切り直し”がしやすいか?
この「仕切り直し」が簡単なツールは、続けやすいです。
Monoxerのように“今日は〇%覚えてたよ”と出してくれるツールは、挫折を「学びの一部」として見せてくれます。
続かないのは、自分のせいじゃない。
ツールとの相性が悪いだけかもしれません。
「うちの子は意志が弱いから…」と責める前に、
ツールを見直すことが、実は大事だったりします。
「選び方」よりも「向き合い方」
最後にもう一度、強調したいことがあります。
それは、「どのツールを選ぶか」以上に、「どう向き合うか」が大切だということ。
たとえば、保護者が「この教材、高かったんだからちゃんとやってよ!」とプレッシャーをかければ、
子どもはやる気をなくすかもしれません。
逆に、「毎日ちょっとずつやってて偉いね」と声をかけることで、
子どもが「続けてみようかな」と感じることもあります。
ツールはあくまで“道具”。
それをどう使うかは、大人の関わり方次第です。
僕はいつも、「その子が“自分で選んだ”と思える学びをサポートする」ことを意識しています。
ぜひ、親子で一緒に「何が合うかな?」と話しながら、
楽しく学べる環境をつくっていきましょう。
📩 LINE登録で、教育テンプレや子育てTipsを毎週お届け!
習慣づくりややる気を引き出すための具体策が詰まっています。