教育・子育ての悩みは、どこに相談すればいいのか分からなくなったときに
勉強が続かない・やる気が出ないときに読むおすすめ記事まとめ
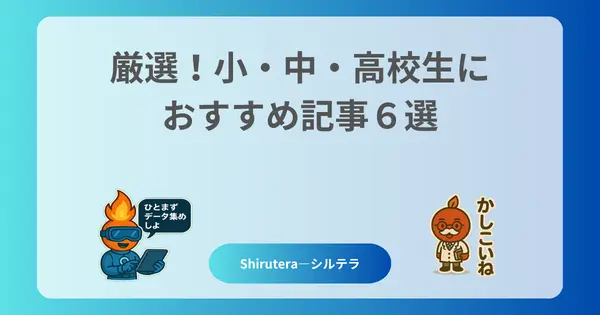
「やる気が出ない」「集中できない」を心理と行動から考える
「勉強しようと思っても続かない」「やる気が出ないまま時間だけ過ぎていく」── そんな悩みを抱えるのは、あなただけではありません。 多くの場合、それは意志が弱いからでも、サボっているからでもなく、 人の行動や習慣の仕組みと、今のやり方が合っていないだけです。
このページでは、「やる気が出ない」「集中できない」「勉強が続かない」と感じたときに役立つ記事をまとめています。 行動科学や心理の考え方をもとに、 どうすれば無理なく動き出せるのか、どうすれば続けやすくなるのかを、 できるだけ分かりやすい言葉で整理しました。
完璧に頑張る必要はありません。 「今のやり方、ちょっと合ってないかも」と感じたときのヒントとして、 気になるテーマから読んでみてください。 小さな工夫が、学び方を変えるきっかけになるはずです。
はじめて読むなら、まずはこの3本から
「塾に通わせるべきか」「スマホと勉強のバランス」「自宅学習が続かない」といった よくある悩みに対して、環境・脳科学・仕組みづくりの3つの視点からまとめた記事です。
-
「うちの子、塾いる?」に答える3条件──“環境”で決める学習スタイルの選び方
塾に行かせるかどうかを「やる気」ではなく「学習環境」で判断する記事です。 家庭で整えられる条件と、塾に任せた方がいい条件の線引きを具体的に解説しています。
-
Fire HD 10は教育用タブレットの決定版!大画面とKindle連携で学習効率を最大化
教室も図書館も、この1台に。高額デバイスの約3分の1の価格でデジタル学習の環境を構築。
Kindle連携、10インチ大画面、ペアレンタルコントロール機能で、学習効率を最大化する最強の相棒です。 -
自宅学習の最適化:継続の仕組み化とツールの使い倒し
見える化・タイマー・ごほうびシステムなど、自宅学習を続けるための 具体的な仕組みづくりを紹介した実践記事です。
関連記事一覧
学習環境、行動科学、オンラインツール、ノートの取り方など、 子どもの学びを支えるための応用テーマをまとめています。
-
お年玉でもらったお金の使い道|後悔しにくい考え方を整理する
お年玉を何に使うか迷ったときに役立つ、お金の使い道の考え方を整理した記事です。 正解を押しつけず、「どう選ぶか」という視点から、 子どものうちに持っておきたい判断の軸をやさしく解説しています。
-
発達心理×スマホ依存──子どもが“勉強しない”理由を脳から読み解く
勉強しない背景にある「脳の発達」と「スマホの報酬設計」を解説し、 怠けではなく“まだ整っていないだけ”という視点から支え方を提案しています。
-
“やる気はいらない”は、ほんとに響くんだなって思った話|行動科学・教育心理
「やる気に頼らず動ける仕組み」が多くの人に刺さった理由を振り返りながら、 否定しない言葉と行動設計の重要性を解説しています。
-
効率的に学べるオンライン学習ツール
家庭で使いやすいオンライン学習ツールを厳選し、 習慣化や親の関わり方とセットで紹介した記事です。
-
【脳科学×教育心理】集中力と記憶力を高める3つの環境要素
光・室温・香りという3つの環境要素から、 集中力と記憶力を高める具体的な整え方を解説しています。
-
【NEW】まとめノートが作れなかったあなたへ──間違いだらけでも、大丈夫な理由
間違いの多さに向き合う苦しさを前提にしたうえで、 失敗を“学びのチャンス”に変えるノート活用法を紹介しています。
📩 LINE登録で、教育テンプレや子育てTipsを毎週お届け!
習慣づくりややる気を引き出すための具体策が詰まっています。