教育・子育ての悩みは、どこに相談すればいいのか分からなくなったときに
子どもが勉強しない・やる気が出ない理由と親の関わり方|教育心理と脳科学で解説
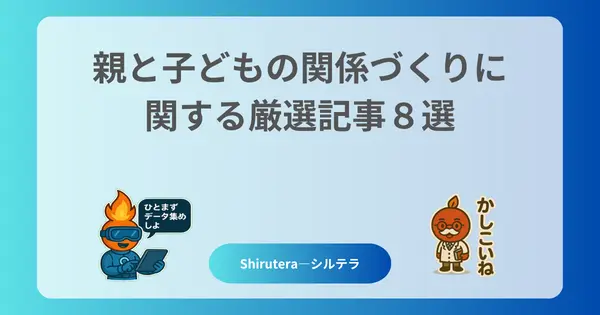
子どもが勉強しない・動かない理由を脳と心理から整理する
「何度言っても勉強しない」「やる気がなさそうに見える」── そんな悩みを抱えながら、つい声かけや接し方に迷ってしまう保護者はたくさんいます。 でも多くの場合、それは親の関わり方が間違っているからではなく、 子どもの脳の特性や心理の仕組みと、家庭での関わり方が噛み合っていないだけです。
このページでは、「やる気」「習慣」「忘れ物」「集中できない」といった家庭でよく起こる困りごとを、 教育心理学や脳科学の視点から整理し、親ができる現実的な関わり方のヒントをまとめています。 叱り方や気合ではなく、環境や仕組みを少し整えることで、 子どもの行動が自然に変わっていくケースも少なくありません。
「言っても伝わらない」と感じたときこそ、関わり方を見直すタイミングです。 完璧な子育てを目指す必要はありません。 この記事を、親子の毎日を少し楽にするための入口として活用してください。
まず読んでほしい3本
-
校長すら知らない制度がある──不登校でも「授業扱い」になる仕組みを解説
不登校や校外での学びが、条件次第で「授業扱い」になる制度が存在します。
しかし現場では共有されにくく、前例主義によって家庭が不利益を被るケースも少なくありません。
教育委員会出身の視点から、制度の仕組み・誤解が生まれる構造・保護者が知っておくべき判断軸を整理します。
-
Fire HD 10は教育用タブレットの決定版!大画面とKindle連携で学習効率を最大化
教室も図書館も、この1台に。高額デバイスの約3分の1の価格でデジタル学習の環境を構築。
Kindle連携、10インチ大画面、ペアレンタルコントロール機能で、学習効率を最大化する最強の相棒です。 -
偏差値は勉強量で決まらない──学習効率を最大化する「インターバルタイマー」という選択
「勉強時間は取っているのに、成果が出ない」──その原因は意志や才能ではありません。
全国模試偏差値73の家庭実践をもとに、学習と休憩の切り替えを自動化する環境設計と、
スマホを使わず集中力を引き出すインターバルタイマー活用を具体的に解説します。
ほかにも読んでほしい記事
-
いじめ相談の判断ガイド|学校・警察・教育委員会、どこに相談すべきか
いじめに直面したとき、「まずどこに相談すればいいのか」を整理した実務ガイドです。
暴力の有無・継続性・緊急性といった観点から、学校・警察・教育委員会の役割を分けて解説し、
状況に応じた相談先の目安を確認できます。 -
子どもの学習習慣が続かない理由と続ける仕組み──行動科学×教育心理の総まとめ
勉強が続かない、宿題に手がつかない、集中が切れる──。
そんな“続かない問題”を、注意資源・習慣形成・親子関係・スマホ依存などの視点から整理。
-
子どもが勉強しない本当の理由|やる気ではなく「習慣」がすべてだった
「やる気がないから勉強しない」と思っていませんか? 教育現場での体験と心理学の研究から、子どもが勉強するかどうかを分けているのは 意志の強さではなく、これまでに積み重ねてきた「習慣」と「学びの経験」だと整理します。 楽しい学習の落とし穴、努力しても身につかないケース、準備や切り替えで止まる理由など、 家庭で起きがちな悩みを構造から読み解く、保護者向けの入口記事です。
-
兄妹でこんなに違う?「学び方」のスタイルから見える子どもの伸びどころ
同じ家庭・同じ環境でも、むすこちゃんとむすめちゃんでは「学び方」がまったく違う──そんな兄妹のエピソードから、 構造派と感覚派という2つのスタイルと、その伸ばし方を整理した記事です。 テスト前の過ごし方やスマホとの付き合い方など、日常の場面に現れる“学びの個性”を手がかりに、 「同じように育てる」のではなく「その子らしい伸び方に合わせる」ためのヒントをまとめています。
-
日本昔話で読み解く 子どもの“心のかたち”大全──こだわり・メタ認知・兄弟差・AI時代の学び
子どものこだわり・メタ認知・兄弟差・AI時代の学び方を、4つの日本昔話で読み解く長編ガイド。
行動の裏にある“心のかたち”を教育心理学と行動科学で整理し、家庭での具体的な関わり方まで解説します。
-
ゆっくり育つ子の地図──焦らず、比べず、信じて待つ【発達心理×脳科学】
「発達がゆっくりな子」を支えるために必要なのは、“焦らせない勇気”と“信じて待つ力”。本ページは、 note連載「ゆっくり育つ子の地図」シリーズと、動画+Shirutera特集ページをまとめたハブ記事です。 家庭や学校でできる具体的な支援方法と心理的背景の理解をセットで解説し、 発達の個性を「遅れ」ではなく「その子のリズム」として捉え直すための新しい地図を提示します。
-
未来の義務教育──文化を超えて希望をつくる
制度の硬直、行政の余裕のなさ、家庭の疲弊──教育を支える三つの柱が同時に揺らいでいる現状を踏まえ、 政治・行政・家庭・地域がどう連携すれば「信頼を再生産できる教育社会」を築けるのかを提言する記事です。 note連載「公立学校義務教育の未来」シリーズ全8回を総括し、現場と制度の両面から義務教育の“未来像”を現実的に描き出しています。
-
なぜ、忘れ物が多い人は何度注意しても減らないのか?
「毎回注意しているのに、また忘れた…」というイライラと、子どもの“悪気のなさ”のギャップ。 その正体は“記憶力の低さ”ではなく、脳のしくみと環境設計のミスマッチにあります。 脳科学と行動心理の視点から「注意では変わらない理由」を解説し、叱るのをやめて“仕組みづくり”で解決するための具体的な工夫を紹介します。
-
やる気がいらない?“自動で動ける習慣”のつくり方
「うちの子、全然やる気がなくて…」という悩みに対して、やる気ではなく「環境」と「仕組み」で動きを作るという視点を提示する記事です。 教育心理学・脳科学・行動経済学をベースに、ToDoリストや時間帯の固定、親の声かけなど、 家庭で今すぐ試せる“自動で動ける習慣づくり”の具体的なステップを解説しています。
-
「うちの子、塾いる?」に答える3条件──“環境”で決める学習スタイルの選び方
「塾に行かせるべきか?」を、学年や点数ではなく“学習環境”から判断するためのチェックリストをまとめた記事です。 塾なしで偏差値73をとったむすこと、塾で学び直すむすめの実例をもとに、 声かけ・集中できる空間・質問できる相手という3条件で家庭と塾の役割分担を整理。 親が“外の力”を使うことを敗北ではなく前向きな選択として捉え直す視点を提案します。
-
「ムリ」と思った中2が英検準2級に合格した話
勉強嫌いで英語も得意ではなかった中2の子が、どのようにして英検準2級に合格したのかを描いた実話ベースの記事です。 特別な塾や高額教材ではなく、「できた」を言語化する声かけや、小さな成功体験の積み重ねに焦点を当て、 子どもの自己効力感を高める関わり方を教育心理の視点から解説しています。 「うちの子にはムリ」と感じている保護者ほど読んでほしい一編です。
-
集中力と記憶力を高める3つの環境要素
「集中できない」「覚えてもすぐ忘れる」という悩みを、子どもの努力不足ではなく“環境要因”から見直す記事です。 音・光・空間といった家庭で整えやすい3つのポイントを、脳科学と教育心理の研究をもとに解説。 リビング学習やスマホ通知、照明などの「当たり前」を少し変えるだけで、認知パフォーマンスを底上げする具体的な工夫を紹介しています。
-
「やさしさ」が子どもを追い詰めるとき──善意が逆効果になる心理
子どものためを思ってかけている言葉や配慮が、かえってプレッシャーや不安を強めてしまうことがあります。 このページでは、「やさしさ」がなぜ暴力的に作用してしまうのかを、教育心理と親子関係の視点から整理。 叱責や放任ではなく、無自覚な期待・先回り・共感のズレが子どもに与える影響を言語化し、 関わり方を見直すための具体的なヒントを提示します。
📩 LINE登録で、教育テンプレや子育てTipsを毎週お届け!
習慣づくりややる気を引き出すための具体策が詰まっています。