教育・子育ての悩みは、どこに相談すればいいのか分からなくなったときに
正しい親が、子どもを壊すとき──やさしさの暴力に気づいていますか?
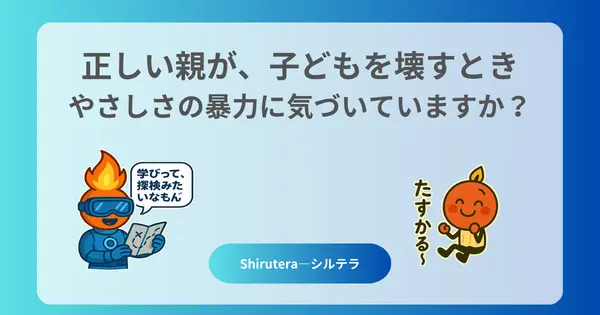
この言葉を、どれだけの親が使い、どれだけの子が傷ついているのか。
教育現場にいた頃、僕はずっと思っていました。
──なぜ、こんなにも多くの“優しい人たち”の中で、
子どもたちが疲れ果てていくのだろう。
親も、先生も、社会も。
誰もが「子どものために」と言うのに、
その子どもたちは、笑わない。
不登校になる。
自己否定を抱え、大人になっても抜け出せない。
その理由を、
僕は「やさしさの暴力」と呼んでいます。
このnoteでは、「正しさ」や「優しさ」が
なぜときに“支配”や“加害”に変わるのかを、
心理学と教育現場の視点から深掘りしていきます。
後半(有料パート)では──
✅ 教育心理・脳科学の観点から「無意識の支配構造」
✅ 家庭内で使える実践ツールと行動テンプレート
をセットで紹介します。
🎁 今回は購入者特典として、
「親が変わるための7つのマイテンプレート」も無料配布中。
あなたの毎日に、すぐに使える“やさしい設計図”です。
「いい親になりたい」
「この子だけは、ちゃんと育てたい」
そう願うことが、なぜかときどき、
誰かを追い詰めてしまう。
僕たちは、いつの間にか
“正しくあること”が当然になっている。
母性神話、教育熱、SNSでの比較…
親でいること自体が、
「見られている立場」にされてしまった。
「子どもが間違えたら、親の責任」
「勉強しないのは、育て方のせい」
「愛情があれば、なんでも乗り越えられるはず」
これらは、どれも“正しそう”に聞こえる。
でも実際には、
その“正しさ”が親自身を縛っている。
あるお母さんが言っていた。
「“優しくできない日”が来るたびに、自分を責めてしまうんです」
「うちの子はいい子なのに、私だけダメなんじゃないかって…」
この言葉は、特別なものではない。
いまの子育てには、こうした“静かな自己否定”が溶け込んでいる。
そして、それを埋めるように
「私は正しいことをしている」と言い聞かせる。
そうして、
“正しすぎる親”が生まれていく。
次の章では、その「正しさ」が
どこから“支配”にすり替わるのかを見ていきます。
「がんばって」
「しっかりしなさい」
「あなたならできる」
どれもポジティブで、優しい言葉。
けれど、状況によってはそれが、
“圧力”にも“命令”にも聞こえてしまうことがあります。
とくに、子どもが疲れていたり、落ち込んでいたり、
「自分はダメだ」と思っているとき──
そんなときに投げられる“正論”は、
ときに心を冷たく閉ざしてしまうんです。
僕が学校現場で出会った子の話。
いつも静かで優等生タイプ。
でも、提出物を忘れたとき、担任の先生にこう言われた。
「あなたらしくないね。がんばってよ」
その子は、それを聞いて泣きました。
でも、それは叱られたからではなく──
“もう、自分らしさを期待されるのが苦しい”と感じたからです。
“やさしさ”が“支配”に変わるとき、
その背景には、こうした期待の重さがあります。
期待される
→ 応えなきゃと思う
→ 応えられない
→ 申し訳なさと罪悪感
→ さらにがんばる or 黙る
こうして子どもは、自分の中に「親の求める自分」をつくっていきます。
その裏で、本当の気持ちや本音は、
少しずつ、押し込められていく。
そして、押し込めた先に残るのは──
「自分がどうしたいか」ではなく、
「どうすれば怒られないか」「がっかりされないか」
これは、自分の人生を生きているとは言えない状態です。
たとえ“愛されている”としても。
こうして、正しいはずの関わり方が、
気づかぬうちに、子どもの自己決定感を奪っていく。
親のやさしさが、
子どもの選択肢を減らしてしまうこともある。
それに気づくことが、最初の一歩かもしれません。
次の章では、心理学の視点から
この「優しい支配」がなぜ起きてしまうのか、
その“しくみ”を深掘りしていきます。
「そんなつもりじゃなかった」
──この一言で、どれだけの“傷”が正当化されてきたんだろう。
親の言葉に悪意はない。
でも、子どもがどう受け取ったかは、まったく別の問題です。
教育心理学では、こうした現象に対して「メッセージの分離性」という概念が用いられています。
つまり──
“送り手の意図”と、“受け手の解釈”は別物だという前提。
たとえば…
「期待してるからね」→プレッシャー
「ちゃんとしようね」→失敗しちゃダメという縛り
「信じてるよ」→裏切ったらダメという不安
ポジティブな言葉ほど、反論できない。
だからこそ、やさしさは、最も静かな支配になる。
📘 自己決定理論(SDT)で見る“やさしさの落とし穴”
心理学では、人が自発的に動くためには3つの要素が必要とされています:
自律性(自分で選んでいる感覚)
有能感(できるという感覚)
関係性(受け入れられているという感覚)
でも、正しすぎる親の言葉には、
ときにこの「自律性」を奪ってしまうものがある。
「◯◯しなさい」→指示された
「ママはあなたを信じてるよ」→選択を誤れない
「ちゃんとできるでしょ?」→できなかったときの罪悪感
つまり、「いい親であろう」とすればするほど、
子どもの“自分で選んだ”という感覚が弱まっていく。
そしてそれが積み重なると、
自分の気持ちや感覚に自信が持てなくなり、
常に“誰かの期待”に合わせて動く子になっていく。
これは、意図せずとも
「他人の評価でしか生きられない子ども」を育ててしまう構造です。
もちろん、親の声かけがすべて悪いわけじゃない。
でも、「子どものため」と信じてやったことが、
実は“正しさの暴力”になっていたことに、
少しだけ立ち止まってみる価値はあると思う。
では、親としてどうすればいいのか。
どうすれば“正しさ”と共に生きながら、
子どもと支配ではない関係を築けるのか。
その答えを、有料パートでじっくり掘り下げていきます。
そして今回は、その「変わるための行動」を支えるために、
無料で使えるテンプレートもご用意しました。
🎁【特典】「親が変わるための7つのマイテンプレート」
→ 記事を読んでくださった方に、無料でプレゼント中です。
→ 本文内リンクからDLできます。
学校って、びっくりするくらい「正しさ」でできてるんです。
チャイムの時間に始まり、チャイムで終わる授業
赤白帽の色まで左右で決められている運動会
「提出物は期限厳守」「整理整頓を徹底しましょう」
それが悪いわけじゃない。
秩序を保つには、ある程度のルールは必要です。
でも問題は、その“正しさ”が誰のためのものかが問われないまま、下に下に流れていく構造にあります。
たとえば──
管理職は、「指導の一貫性」を理由に、個々の教員に“同じ対応”を求める。
教員は、「全体の調和」を理由に、子どもに“同じ態度”を求める。
そして子どもは、家庭で「学校でこう言われたから」と、親に同じ価値観を求める。
これはまさに、“正しさの連鎖”です。
しかも、その正しさには“責任”がついて回る。
子どもが問題行動を起こせば「指導が甘い」と言われ
提出物が揃わなければ「担任が機能していない」と責められ
不登校になれば「家庭と学校の連携が…」と曖昧に語られる
正しさを守らなければならない。
守れなかったら、誰かのせいになる。
こうして現場は、守り続けることに疲弊していく。
僕自身も、現場にいた頃、こう思っていた。
「この子には、このタイミングでは叱らない方がいい」
そう思っても、マニュアルに沿って注意しなきゃいけなかった。
「ほかの子との公平性を考えて」
「一貫性のある指導をするために」
でも、それって本当に「教育」だったのかな。
ただの“制度維持”だったんじゃないか。
そして、現場のそういう動きは、
いつしか保護者にも感染していく。
「みんなと同じようにできるように」
「迷惑をかけない子に育てないと」
「ちゃんと挨拶できるようにしないと」
この“ちゃんと育てなきゃ”という意識こそ、
教育現場で生まれた“正しさ”が、家庭に伝播していった結果なのかもしれません。
子どもにとって、
家は「自分らしくいられる場所」であってほしい。
でも、学校のように“正しさ”が支配してしまったら、
子どもは、もう逃げ場がない。
次章では、こうした“正しさ”がなぜ起きるのか、
その背後にある脳の仕組みに切り込んでいきます。
親として、先生として、
「そんなつもりじゃなかった」と思う場面は山ほどある。
でも、“つもり”と“現実”は、脳の中ではまったく違うことだと、心理学と神経科学は教えてくれます。
🧠 システム1とシステム2──「反射」と「思考」
行動経済学者ダニエル・カーネマンの提唱した概念に、
人の思考は2つのシステムから成り立っているというものがあります。
システム1:直感・反射的な判断(早い、無意識、自動)
システム2:論理的・熟考による判断(遅い、意識的、努力が必要)
子どもに「早くして!」と怒ってしまうとき、
僕たちはたいていシステム1で反応しています。
朝の忙しい時間
疲れている夜
気持ちに余裕がない瞬間
このとき、理性よりも反射が勝ちます。
つまり、「やさしくしたい」という意思よりも、
「早くしてくれ」という脳の省エネ欲求が前に出てしまう。
🧩 脳は“思いやり”より“効率”を優先する
脳には、現実を“簡略化”して処理しようとする傾向があります。
これを「認知バイアス」といいます。
子どもが泣く=わがまま
片づけない=やる気がない
宿題しない=怠けてる
こうした“わかりやすい決めつけ”は、脳にとってはラクなんです。
でも、その分だけ、相手の背景を想像する力が省かれてしまう。
だから僕たちは──
「怒るつもりじゃなかった」けど怒って、
「否定するつもりじゃなかった」けど否定してしまう。
それを“無意識の加害”と呼びます。
しかもこの無意識の加害は、
繰り返すほど「正しいこと」として脳にインストールされてしまう。
何度も怒るうちに、怒ることが“当たり前”になる
「言うことを聞かせる」ことが、“教育”になってしまう
子どもに謝られれば、それで自分は“いい親”だと感じてしまう
僕たちの脳は、
「自分が悪かった」と思いたくない。
だから、“自分の正しさ”を証明する記憶ばかりを残そうとするんです。
これは、誰もが持っている仕組みです。
でも、それに気づかないままでいると──
やさしさという名の下に、人を壊してしまうこともある。
次章では、その“壊される側”、
つまり子どもがこうした無意識の関わりの中で
どう感じ、どう「我慢」していくのか──
そのプロセスを見ていきます。
子どもは、親の顔色をよく見ています。
大人が思っているよりも、ずっと繊細に。
さっきの言い方、マズかったかな…
これを言ったら、また怒られるかも…
今のうちに片づけておこう、じゃないと…
こうした「読み取り」と「先回り」が、
子どもの中で日常的に起きていること、気づいていますか?
💢 いい子症候群──“期待に応える”という仮面
最近は「いい子症候群」という言葉も広がりつつあります。
これは、
✅ 親や先生の期待に応えようと、過剰に“がんばる”子どもたち
✅ 本音や感情を抑え、自分よりも周囲を優先してしまう傾向
を指します。
彼らは、叱られないように行動するのがうまい。
でもそれは、“自分を守るための知恵”です。
実はこのタイプの子こそ、
“やさしさの暴力”にもっとも静かに、深く、傷ついていることがあります。
「がんばってね」
「信じてるよ」
「あなたなら大丈夫」
こうした言葉に、応え続けようとして──
本当は疲れてるのに「うん」と返事してしまう。
でも、がんばっても結果が出なかったとき、
彼らは「自分が悪い」と思うしかなくなるんです。
これは、自責性の過剰化と呼ばれる心理傾向で、
将来的に「自己肯定感の低下」や「うつ傾向」「過剰適応」につながるリスクがあります。
🤐 “感情の抑圧”は、やがて身体に出てくる
心理学では、「抑圧された感情は、身体に現れる」と言われています。
頭痛や腹痛(原因不明)
不登校や登園渋り
チック症状や吃音、一過性の沈黙
これらはすべて、「話せない」ことによって現れる“サイン”かもしれません。
子どもは、言葉で説明できないからこそ、
行動と身体で“無意識のSOS”を出してくる。
でも、大人はそれに気づけないことが多い。
むしろ、「サボり」「甘え」として片づけてしまう。
だからこそ、
親や教育者は「異変の裏側」にある感情に気づく視点を持たないといけない。
次の章では、そんな私たち大人が、
どうやって“正しさ”を手放し、
子どもと向き合う行動に変えていけるのか──
その具体的な方法をテンプレートと共に紹介します。
「変わらなきゃ」と思うことはある。
でも、実際に“変わる”って、本当に難しい。
なぜなら──
✅ 忙しい
✅ 習慣が染みついてる
✅ 自分を変えるって、ちょっと怖いから
だから僕は、「行動テンプレート」という発想を提案します。
🧩 行動テンプレートとは?
思考や気分に頼らず、“先に行動の選択肢を決めておく”という技術
これは行動科学でも使われている方法で、
✅ 習慣を変える
✅ 自己肯定感を下げない
✅ 継続できるようにする
ための有効な仕組みです。
💡 たとえば…
怒りたくなったときのチェックシート
1日の終わりに書くフィードバック欄
「子どもへの言葉づかい」言い換えテンプレ
「毎回ちゃんと考える」は、正直ムリ。
だから、「迷ったときに見る紙」が必要なんです。
🎁 無料配布テンプレート:「親が変わるための7つのマイテンプレート」
購入者特典としてお渡しするテンプレートには、次のような内容が含まれています。
1️⃣ 怒りのトリガー記録シート
「どんなときに、どんな言葉で怒ってしまったのか」を書き出して、自分の“パターン”を整理するためのシートです。
2️⃣ 子どもへの声かけチェック表
「命令になっていないか?」「感情を押しつけていないか?」を、感情ラベルと一緒に振り返ることができます。
3️⃣ “選ばせる”ための言い換えリスト
「早くして」ではなく「どっちにする?」など、日常で使える“やさしい選択肢”の言い換えをまとめています。
4️⃣ 1日1回のフィードバックメモ
その日に“子どもに伝えたかったこと”と、“実際に伝えられたこと”を並べて書けるシートです。
5️⃣ 親自身へのリカバリー用語
「私はちゃんとやってる」「今日はここまででいい」など、自分の心を落ち着かせる“セルフトーク”集です。
6️⃣ しんどかった日の回復リスト
「家族に言える一言」「3分でできる1人時間」など、親が“やさしく切り替えるため”の小さな行動ヒントを並べました。
7️⃣ 週1レビュー:うまくいったこと3つ
つい見逃しがちな“いい場面”を意識的に残すためのテンプレ。ポジティブ記憶を“習慣化”する仕組みです。
📩 テンプレートはPDF形式で、印刷してもスマホでも使えます。
note本文の下部からLINE登録すれば、すぐに受け取れます!
📥 ダウンロード方法は、note本文の下部にあるリンクから。
僕らは、どうしたって“正しさ”から逃れられない。
子どもにはちゃんと育ってほしい
社会で困らないようにしてあげたい
周りから「いい親だね」と思われたい
こう思うことは、決して悪じゃない。
むしろ、それは愛の形だ。
でも、問題は──
その「正しさ」を、“誰のため”に使っているかということ。
もしもそれが、
・子どもをコントロールするための言葉になっていたら
・自分の不安を打ち消すためのルールになっていたら
・誰かの目を気にして発動するマニュアルになっていたら
その“正しさ”は、一度、見直してみてもいい。
親子関係は、
「対等」になれるものではない。
でも、
“誠実であろうとする関係”にはなれる。
怒ってしまうこともある。
うまく伝えられない日もある。
でも、そのあとに、
「伝え方を間違えたかもしれない」と言えるかどうか。
それだけで、関係は変わっていく。
完璧じゃなくていい。
揺らいでもいい。
その中で、自分の言葉を選び直していける人が、
「優しさ」と「正しさ」を同時に持てる親になるんだと思う。
ここまで読んでくれたあなたに、
もう一度、伝えたい言葉があります。
「その言葉は、誰を守るために選びましたか?」
少しずつ、選びなおしていきましょう。
一緒に、明日から。
🎁 無料テンプレート配布中
親が変わるための7つのマイテンプレート(PDF)を無料で配布中です。
ダウンロードはLINEからすぐ可能です。
🟢 LINE登録はこちら(登録後「やさしい暴力」と入力してください)
🧭 もっと深く学びたい方へ
心理学・脳科学・教育に基づいた信頼性のある情報は、
総合教育メディア「シルテラ」で継続発信しています。
📩 LINE登録で、教育テンプレや子育てTipsを毎週お届け!
習慣づくりややる気を引き出すための具体策が詰まっています。