教育・子育ての悩みは、どこに相談すればいいのか分からなくなったときに
「うちの子、塾いる?」に答える3条件──“環境”で決める学習スタイルの選び方
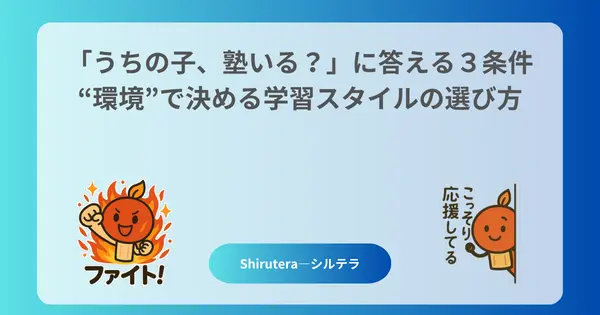
「塾は必要?」という迷いに、環境から答える──我が家の実例とチェックリスト
「先生、うちの子、塾に行かせた方がいいですか?」
これは、僕が担任をしていたころ、よく保護者の方から聞かれていた質問です。
特に、小学校4年生くらいから、この相談がぐっと増えてきたことを今でも覚えています。
テストの点数が気になったり、まわりの子が塾に通いはじめたり。
そんなタイミングで、「うちも行かせた方がいいのかな…」と迷う気持ちは、とてもよくわかります。
でも、僕がいつもお伝えしていたのは──
「何年生だから」や「テストが〇点だったから」といった“数字”だけで判断するのではなく、
その子の“今の学習環境”を見て考えてみませんか?ということでした。
塾に行くかどうかは、その子の“やる気”や“能力”の問題ではなく、
「どれだけ学習に集中できる環境が整っているかどうか」で決めていいんです。
この記事では、我が家のむすこ(塾なし)と、むすめ(塾あり)という実例をもとに、
判断のヒントとなる3つの視点をご紹介します。
むすこは塾へ行っていませんが全国模試偏差値73です。
塾に行けばいいというわけではないということが、これで分かりますよね。
お子さんに合った“学び方”を見つける、きっかけになればうれしいです。
第1章:その悩み、「本人のやる気不足」ではありません
「家で全然勉強しないんです。塾に行かせた方がいいでしょうか?」
これは、僕が現場で保護者の方から最もよく聞かれてきた言葉の一つです。
子どもの学年が上がるにつれて、この相談は増えていきます。
特に、小学校4年生を過ぎたあたりから「このままでいいのか」と悩み始める親御さんが多くなります。
でも、そのとき僕はいつもこう答えていました。
「お子さんの“やる気”がないのではなく、“学習する環境”が整っていないだけかもしれませんよ」
これは、僕自身の家庭でも強く実感していることです。
我が家には、現在中学3年生のむすこと、中学1年生のむすめがいます。
実はこの2人、まったく逆の道を歩んでいます。
むすこは塾に通っていません。一方、むすめは塾に通っています。
「兄は塾なしでいけたのに、妹はなんで?」とよく聞かれます。
たしかに、むすこは自分で予定を立て、学校の自習の時間で机に向かう習慣が早くからできていました。
僕たち親が「勉強しなさい」と言う前に、もう取りかかっている。
分からないことがあっても、まずは自分で調べてみて、最後の手段として僕に聞いてくる──そんなスタイルでした。
でも、むすめは少し違います。
まず、「何をすればいいか」がわからない。
そして、家にいるとついスマホを触ったり、他のことが気になって集中が続かない。
リビングも静かとは言えず、兄のオンライン授業の声や、洗濯機の音、僕らの電話の音……気が散る要素がたくさんあります。
そして決定的なのは、むすめにとって「わからない問題をすぐに聞ける相手がいない」ことでした。
僕も日中は仕事、夜は家事や別の仕事が重なって、毎回手厚く対応できるわけではありません。
そんな状況で、「ちゃんとやりなさい」と言うのは、むすめにとっては酷だったと思います。
むすこがうまくいったのは、本人の性格や能力というよりも、
「集中できる場所があって、支えてくれる人がいて、学ぶ流れができていた」
──つまり、“学習するための環境”が自然に整っていたからなんです。
反対に、むすめの場合は、その環境を整えること自体に家族のエネルギーがかかる。
だから、塾という“外の力”を借りる選択をしました。
ここで大事なのは、「本人のやる気を信じるかどうか」ではなく、
「子どもが自然に学習に向かえる状況があるかどうか」という視点です。
やる気はあっても、環境が整っていなければ、集中も継続もできません。
「塾が必要かどうか」は、子どもの性格や家庭の理想論ではなく、
現実的に“今の家庭に何があるか、ないか”で考えていい。
むすことむすめはどちらも、頑張っている子です。
でも、それぞれに合った“学ぶ環境”を選ぶことで、
結果的にそれぞれのスタイルで前に進めているんだと思います。
第2章:学習時間は“やる気”ではなく“環境”で決まる
「やる気がない」「集中力がない」
そんなふうに、子どもを評価してしまったことはありませんか?
でも実は、子どもが机に向かえない原因の多くは、本人の気分や性格ではなく、
「学習に向かえる環境が整っていないこと」にあります。
教育心理学の分野では、
「人の行動は“環境のきっかけ”と“その結果”によってつくられる」と言われています
(行動分析学のABC理論など)。つまり、集中して学べるかどうかも、
その子の“学習環境”に大きく左右されるということです。
ここで言う環境とは、例えば次のようなものです。
- 親から「勉強しなさい」と言ってもらえるかどうか
→ 忙しさや気まずさから、つい声かけが減っていないか? - 静かで集中できる空間があるかどうか
→ テレビの音、兄弟の声、スマホの通知…気が散る要素が多すぎないか? - わからない問題をすぐに聞ける相手がいるかどうか
→ 親が学習内容に自信がなかったり、質問対応の時間が取れなかったりしていないか?
このどれかが欠けていると、子どもは「やろうと思ってもできない」状態になります。
そして何より大事なのは、“子どもが1分でも長く、机に向かえる状況ができているかどうか”です。
むすこの場合、これらの環境が学校にそろっていたため、自分の力で学習を進めることができました。
休日は、僕が声をかけなくても、リビングで集中し、自分で教科書を読み進めたり、
タブレットで調べたりできたんです。
でも、むすめは、環境とむすめ自身とが合っていませんでした。
リビングの小さい音が気になり、机も散らかりがち。
わからない問題を質問できる相手が近くにおらず、
「やりたいけど、やれない」状態が続いていました。
だからこそ、むすめには塾が必要だったのです。
塾という場所には、勉強に集中できる空間と、わからないところをすぐに教えてくれる講師、
そして「学習に向かう流れ」が用意されています。
つまり、家庭にない“環境”を外から借りてくるための手段として塾を選びました。
ここでお伝えしたいのは、「塾が必要かどうか」は本人の学年や成績などの見た目ではなく、
“今の家庭で学習環境がどれだけ子どもと合っているか”で決めるべきです。
やる気を出せと言うよりも、やる気が自然と湧きやすくなる環境を、どこで用意するか。
それが、塾という選択の本質だと、僕は考えています。
第3章:「家庭で整う」or「塾に任せる」判断基準はここ
「家庭でサポートできるなら、それに越したことはない」
──そう思う保護者の方は多いはずです。
けれど、現実的には仕事や家事に追われて、なかなか思うように関われない。
わからない問題を教える自信がない。静かな空間を確保するのもむずかしい。
そんな悩みを、僕もたくさん聞いてきました。
そこで、塾に行かせるかどうか迷ったときに使える、
3つの視点をチェックリストとしてご紹介します。
これは「やる気があるか」ではなく、
「学習時間を確保できる環境があるかどうか」を見きわめるための目安です。
これらのチェックリストは、僕が学級担任をしていた時に実際に使っていたものです。
かなりご好評をいただいていたので、多くの人の役に立つと思います。
✅ チェックポイント1|声かけの土台はあるか?
- ☐ 子どもに「勉強しなさい」と言うと素直に勉強する
- ☐ 声かけを“習慣”として続ける余裕やリズムがある
- ☐ 親子のコミュニケーションが安心感のあるものになっている
→ 声をかけることが、ストレスや衝突のもとになっている場合、
家庭学習が長続きしづらくなります。
✅ チェックポイント2|静かで集中できる場所があるか?
- ☐ テレビ・スマホ・兄弟の声など、気が散る要素が少ない
- ☐ 学習に使える机・椅子・照明などが整っている
- ☐ 子ども自身が「ここなら集中できる」と思える場所がある
→ 勉強しようと思っても、音や視覚的な刺激が多いと、集中は続きません。
✅ チェックポイント3|わからないときに、誰かに聞けるか?
- ☐ 親が内容をある程度把握できている(または調べる余裕がある)
- ☐ 子どもが「質問しても大丈夫」と感じている
- ☐ タイミングを逃さずに教えられる時間の余裕がある
→ 子どもが「わからないままにしておく」ことが続くと、
勉強そのものを避けるようになります。
我が家の例で言えば、むすこはこの3つすべてが学校の自習時間に整っていました。
静かな空間、必要なときの支援、自分でスケジュールを立てて勉強できるだけの土台。
それがあったからこそ、塾に行かずとも、学習時間をしっかりと確保できたんです。
一方で、むすめはこのチェックのうち、2つ以上が家庭では整いませんでした。
我が家は共働きのため勉強しなさいという人が家にいません。
小さな音でも気になってしまう。わからないところをすぐに聞く人がいない。
──これでは、どれだけ「がんばれ」と言っても、勉強に向かえないのは当たり前です。
だからこそ、塾という“整った環境”を使うことに決めました。
大事なのは、「塾が必要かどうか」ではなく、“子どもが学習に向かえる環境が、どこにあるか”なんです。
それが家庭にあるならそれでいいし、ないなら外の力を借りたっていい。
選択肢の幅を広げてあげることが、結果的に子どもを支える一番の近道になることもあります。
第4章:子どもに合った「学びの場所」を選べばいい
ここまで読んでくださったあなたは、きっと「塾に行かせた方がいいのかな…」と迷いながらも、
子どもにとって一番いい選択をしたいと願っている方だと思います。
その気持ちがある時点で、もうすでに“いい親”だと僕は思います。
子どもに合った学び方は、「家庭か塾か」という単純な二択では語れません。
家庭で環境が整えばそれでいいし、整えるのが難しいときは、塾の力を借りてもいい。
どちらが正しいとか間違っているとかではなく、
子どもが1分でも長く机に向かえる環境を用意できているかどうか
──それが一番大切なんです。
僕は、むすこが塾に通わずに偏差値73をとったことを自慢したいわけではありません。
「自力で学べる力がある子」と「自力だとうまくいかない子」がいる、
というただの事実をお伝えしたかっただけです。
そして、むすめは塾という場所で、少しずつ集中できる時間が増えてきました。
塾の先生とのやりとりを通じて、「わからないところは聞いていいんだ」と思えるようになり、
自信をつけていっています。
家庭でのサポートがうまくいかないと感じるとき、
親としては「自分の力が足りないのかも…」と
落ち込んでしまうこともあるかもしれません。
でも、それは違います。
塾を“選ぶ”ということは、子どもにとって今必要な環境を“整えてあげる”という、
親の立派な選択なんです。
勉強のスタイルは、人それぞれ。
性格も、得意なことも、集中できる場所もみんな違います。
だからこそ、「この子にはどんな場所が合っているのか?」
という視点で考えることが大切です。
あなたのお子さんが、のびのびと、自信をもって学べる環境に出会えますように──
その願いを込めて、この記事を書きました。
まとめ|塾に行かせるべきか迷ったときの3つの視点
塾に行くかどうかを決めるとき、「学年」や「点数」だけで判断するのではなく、
次の3つの視点で“学習環境”を見直してみましょう。
- ✅1|声かけができる関係があるか
親子の関係がこじれずに、自然な声かけができている? - ✅2|静かな学習空間があるか
集中できる場所や時間が、家庭の中にある? - ✅3|わからないときに聞ける人がいるか
子どもが安心して質問できる環境がそろっている?
この3つのどれかが難しいなら、塾は“子どものための学習環境”を外から補う手段になります。
家庭で整うならそれでよし。整わないときは、迷わず外の力を借りればいい。
大切なのは、「どこで学ぶか」ではなく、「子どもが学びやすい場所を選ぶこと」です。
📌 お知らせ&導線
この記事が参考になった方は、ぜひフォローをお願いします。
今後も、子育て・学習・脳科学の視点から、親子の学びを支える記事をお届けします。
- 🧠 教育メディア【Shirutera】→ Shirutera
- 🗂 他の記事も見てみたい方はこちら → マガジン一覧
- 👣 LINEでも更新情報を配信中です → LINE登録はこちら
- 🧸 マッチくんLINEスタンプはこちら → スタンプを見る
📩 LINE登録で、教育テンプレや子育てTipsを毎週お届け!
習慣づくりややる気を引き出すための具体策が詰まっています。