教育・子育ての悩みは、どこに相談すればいいのか分からなくなったときに
やる気がいらない?“自動で動ける習慣”のつくり方
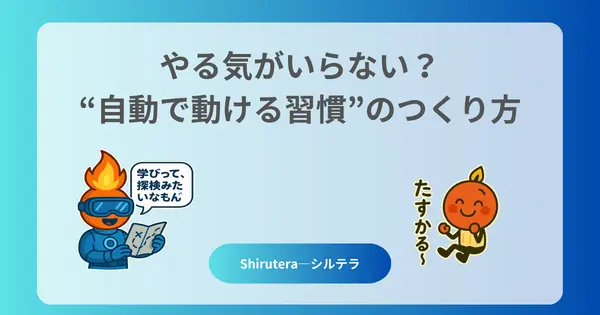
「やる気が出ない」は普通のことです
「やる気が出ない…」
この言葉、どこかで聞いたことありませんか? もしくは、今まさにそう感じている人もいるかもしれません。
実はこれ、子どもだけでなく大人にもよくある自然な状態なんです。人間の脳は基本的に「ラクをしたがる」ようにできています。
だから、意志だけで動こうとするのは、じつはかなり難しいこと。
そんな中で、「どうすれば自然に行動できるのか?」という問いに対して、最近注目されているのが「習慣」の力です。
やる気よりも「仕組み」が大事
教育心理学や脳科学の分野では、「やる気を出そうとするよりも、やる気がいらない仕組みをつくる方が効果的」だと言われています。
たとえば、アメリカのスタンフォード大学で行動科学を研究していたBJ・フォッグ博士はこう言います。
「人は小さな行動を毎日繰り返すことで、大きな変化を起こす」
この考え方は「Tiny
Habits(小さな習慣)」と呼ばれており、いきなり“30分勉強”とか“10キロ走る”みたいな高い目標を立てるよりも、
「1分だけ」「机に座るだけ」のような小さな行動を繰り返す方が、結果的に継続しやすいという理論です。
脳が“やる気”を生むのは「行動のあと」
ここで意外な事実をひとつ。やる気というのは「何かを始めたあと」に出てくるものだということ。
これを「作業興奮」と呼びます。つまり、やる気がないときは「行動→やる気」という順番を意識することが大切なんです。
僕自身も、「原稿書くのめんどくさいな…」と思っていても、とりあえずPCを開いて、1文だけでも書き始めると、
いつのまにか集中モードに入っていることがあります。
これが「脳が動き出すトリガー」になるんですね。
習慣をつくるには、最初のハードルを下げよう
子どもに勉強を習慣づけさせたい。自分自身も運動や読書を習慣にしたい。
そう思ったときに大事なのは、「とにかく始めることのハードルを下げる」ことです。
- ノートを開くだけでOK
- ランニングシューズを履くだけでOK
- タイマーを1分だけセットしてみるだけでもOK
最初から完璧を求めず、「始める」ことにだけフォーカスすると、“やる気が出る前に行動する”という仕組みがつくれます。
子どもにも使える!「習慣」の設計
教育現場でも、この習慣化の考え方はとても効果的です。
たとえば、宿題を毎日だらだら先延ばしにしていた子どもに対して、
「机に座ったらまず“今日のやること”を1分だけ書き出そう」と声かけをしただけで、
次第に自分から勉強を始めるようになったケースがあります。
これは“行動のハードル”を低くしたことで、脳の「作業興奮」を活かせた好例です。
習慣は“自分を責めない武器”にもなる
僕たちはつい、行動できない自分を責めてしまいます。
でもそれって、意志や根性の問題じゃないんですよね。ただ、脳の仕組みを知らなかっただけ。
「やる気がないからダメなんだ」じゃなくて、
「やる気がなくても動ける仕組みを作ればいいんだ」って気づけたとき、
すごく気持ちが楽になります。
そしてそれは、誰でも今日から始められます。
おわりに:仕組みで動ける自分を作ろう
今回の動画では、「やる気に頼らず習慣で動く」ための考え方を紹介しました。
やる気が出るのを待たなくていい。意思の強さに頼らなくていい。
まずは“1分だけ動く”ことから始めてみませんか?
あなたの日常が、少しずつ変わっていくはずです。
📌 習慣づくりや教育心理に関する動画や記事は、今後も定期的に発信しています。
「学びって、もっと気楽でいいんだ」と感じてもらえるような情報を、これからも届けていきます。
気になった方は、#名無しマッチ で検索してフォロー&保存してもらえるとうれしいです!
関連リンク
📩 LINE登録で、教育テンプレや子育てTipsを毎週お届け!
習慣づくりややる気を引き出すための具体策が詰まっています。