教育・子育ての悩みは、どこに相談すればいいのか分からなくなったときに
自宅学習の最適化:効率的に学べるオンライン学習ツール
2025年4月15日
タグ:#子育て #勉強法 #オンライン学習
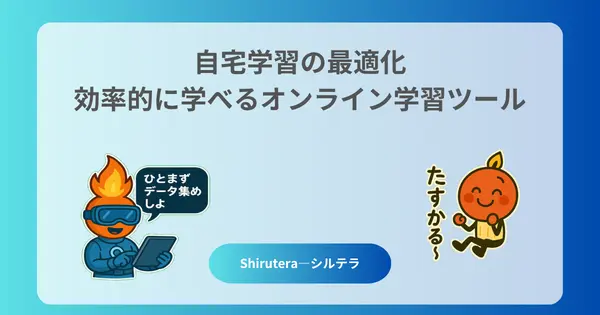
記事を読んでくださり、ありがとうございます。
こんにちは、名無しマッチです。
初めての方のために自己紹介をします。
目次
- 学習が続かない理由、続けられる人の違いって?
- 僕の独学ヒストリーと“芯のある学び”のつくり方
- “芯”を支えるツールの選び方
- おすすめツール紹介
- 継続のコツと学びを深める関わり方
- 学びをもっと楽しくするコツと、マインドセットの整え方
1.学習が続かない理由、続けられる人の違いって?
「うちの子、やる気はあるんですが、どうしても勉強が続かなくて…」
これは、僕が教員時代に何度も耳にした保護者の言葉のひとつです。
そして実際、勉強って続けるのが難しいんですよね。大人でもそうです。
でも、だからこそ今の時代、勉強を“努力”や“根性”に頼らないやり方が必要です。
そのための鍵になるのが、オンライン学習ツールの存在です。
最近では、タブレット1枚で授業を受けたり、質問したり、復習したりできる時代になりました。
教室の外でも、自分のペースで学べる環境が整いつつあるんです。
でも…正直な話、
「たくさんありすぎて、どれを使ったらいいのか分からない」
「結局、続かない」
そんな声もよく聞こえてきます。
僕も実は独学が大好きで、これまでにいろんなツールや教材を使ってきました。
趣味も多くて、仕事にも活かしてきた経験があります。
今回は、そんな僕の独学の経験と、教育現場での実践をふまえて、
「どんなツールを選び、どう使えば、“自宅学習”を効率的で楽しいものにできるのか?」
について、シリーズでお届けします。
第一回となるこの記事では、まず僕の独学経験と、独学に必要だった“ある視点”についてお話ししたいと思います。
それが、「学びに一本芯を通す」ということです。
これは、僕がオリジナルの授業方法「意味調べ大会」や「立ち歩き対話法」などを生み出す過程で、何より大切にしていた視点でした。
そして、この“芯”を意識した学びこそが、これから紹介するオンラインツールの選び方にも、しっかりとつながってくるのです。
次回の記事では、その“芯”を持った学びがどうして生まれたのか、
そして、具体的におすすめできるオンライン学習ツールについてご紹介していきます。
まずはここまで。この記事が、あなたやあなたの大切な誰かにとって、学びのきっかけになることを願っています。
2.僕の独学ヒストリーと“芯のある学び”のつくり方
僕は、独学が好きです。AIを使って新しいことに挑戦するのも、趣味の幅を広げるのも、基本的には自分で調べてスタートします。
教育の世界でも、それは同じでした。
「意味調べ大会」(←記事があるのでリンク貼ってます)や「立ち歩き対話法」(後日公開予定)など、僕が現場で実践してきた指導法は、どれも教科書や指導書に載っていたわけではありません。
じゃあ、どこから生まれたのか?
答えは、“学びに一本芯を通す”という視点からでした。
僕は教員1年目から、指導書をほとんど読んでいませんでした。
先輩に「読んどけ」と言われても、自分のやりたいことと合っていないと、どうしても頭に入らなかったんです。
その代わり、自分が「面白い」と思える学びの形を追いかけました。
自分なりにテーマやコンセプトを決めて、教材を読み直したり、他の学校の実践を調べたり、子どもの反応を観察したり。
そうやって、“自分の軸”を持ちながら学び続けたんです。
その結果、子どもたちにとっても楽しい授業ができるようになりました。
子どもは正直です。先生が面白がっていない授業には、すぐに飽きます。
逆に、先生がワクワクしていると、自然とクラスも動き出す。
この「芯のある学び方」は、どんな学習にも応用できます。
オンライン学習でも、それは同じです。
「何を学ぶか?」よりも、「なぜ学ぶのか?」
そこが自分の中で明確であれば、どんなツールでも“学びの道具”として使えるようになります。
そして逆に、“芯”がないと、どんなに優れたアプリを使っても、すぐに飽きてしまいます。
そういった「芯のある学び」を支えるオンライン学習ツールの選び方と、
具体的なおすすめツールについてご紹介します!
3.“芯”を支えるツールの選び方
ここまで、「自宅学習に必要なのは“芯”」という話をしてきました。
では、その芯を支えるには、どんな学習ツールを選べばいいのでしょうか?
ここでは、僕が選ぶときに大事にしている3つのポイントをご紹介します。
①:学習のプロセスが“見える化”されていること
ただ動画を見るだけ、問題を解くだけでは学びは定着しません。
「自分がどこまでできて、何が苦手なのか」を視覚的に確認できるツールは、
学習の継続性を支える大きな力になります。
- 学習記録がグラフやカレンダーで表示される
- AIが弱点を自動で分析・フィードバックしてくれる
②:自分のペースで進められる設計
「毎日30分だけ」「1単元ずつ」など、習慣にしやすい構成かどうかが重要です。
とくに部活や習い事が忙しい子には、“すき間時間”をうまく使えるかがカギになります。
③:楽しい or 自分に合っている
これはとても大事!どんなに機能が優れていても、「つまらない」と思ったら続きません。
その子にとって「気軽に使える」「デザインが好み」「音声が聞き取りやすい」など、
感覚的な“合う・合わない”も大切な判断基準です。
4.おすすめツール紹介
ここでは、前回紹介した3つの視点をもとに、僕が実際に使ったことのあるツールの中から
「これならおすすめできる!」というものを3つ紹介します。
それぞれの特徴を、子ども・保護者・教員の視点からまとめているので、
自分に合ったものを探すヒントになれば嬉しいです。
① スタディサプリ高校・大学受験講座
- おすすめポイント:
- 授業動画の質が高く、どの学年でも“基礎の復習”がしやすい
- 科目や単元を自分で選べるため、苦手な部分の克服に最適
- 料金が安く、家計に優しい(小中高:月2,178円)
- 向いている人:
- 学校の内容を少し取りこぼしている子
- 復習中心に、自分のペースで学びたい子
- 教員が“教材代わり”に使うのもアリ!
② Monoxer
- おすすめポイント:
- AIによる反復学習で「忘れない」記憶を支援
- 語彙や英単語、歴史年号など「覚える系」に強い
- 学習の履歴や記憶度がグラフで見える
- 向いている人:
- 暗記が苦手な子、反復練習が続かない子
- 高校入試や英検など、試験対策をしたい人
- 語彙力や記憶力に課題を感じている保護者や先生
③ デキタス
- おすすめポイント:
- 小中学生向けで、アニメ風のキャラがナビしてくれる
- 授業の内容が5分程度の動画にまとまっていてわかりやすい
- ゲーム感覚でポイントがたまり、達成感が得られる
- 向いている人:
- 低学年〜中学生の「勉強ギライ」にアプローチしたい保護者
- 家庭での予習・復習の“入り口”に
- 自学習に抵抗感がある子ども
この3つは、僕が実際に使って「これはいいな」と感じたツールです。
もちろん、すべての子に合うとは限りませんが、選ぶ際の視点を持っていると「相性が良いか」が見抜けるようになります。
そして何より、
「子どもが“学ぶこと”を嫌いにならないために」
できるだけストレスの少ない環境を整えることが、僕たち大人にできることだと思います。
また、自分自身で学びのスタイルを選べる子に育ってほしいと願うばかりです。
5.継続のコツと学びを深める関わり方
これまでの記事では、ツール選びの視点や、おすすめのサービスについてご紹介してきました。
でも、どんなに優れたツールでも、実は“継続”できなければ意味がないんですよね。
今回は、「自宅学習を習慣にするコツ」と「子どもとの関わり方」について、
保護者や教員の視点から考えてみたいと思います。
① 学びが続く家庭の特徴
僕がこれまでに関わってきた子どもたちの中で、「自宅学習が自然と続いている子」には、ある共通点がありました。
それは、“学ぶことが生活の一部になっている”ということ。
特別な環境ではなく、当たり前のように「ちょっと勉強してくる」「終わったら報告する」という文化があるんです。
もちろん、最初からそうだったわけではなく、家庭のちょっとした工夫や関わりが積み重なって、そうなっていったケースが多いです。
② 習慣化のためのコツ
- 時間と場所を決める
「夕食の前の30分はリビングで」など、ルールを一つ決めるだけでも習慣化の第一歩になります。 - 見える化する
学習の記録をカレンダーやシールで可視化すると、子どもは達成感を得やすくなります。
とくに低学年では、目に見える成果が「続ける力」につながります。 - 成果ではなくプロセスを褒める
「○点取ったね!」よりも、「毎日頑張ってるね」「昨日より早く終わったね」と声をかけてあげると、学習に対する自信が育ちます。
③ 親や先生の“関わりすぎない見守り”
「ちゃんとやった?」「なんでできないの?」と口出ししすぎると、子どもはプレッシャーを感じてしまいます。
反対に、まったく無関心だと「どうせ見てないし…」とモチベーションが下がります。
ちょうどいい関わり方は、“関心を持って、干渉しない”こと。
- 「今日は何やったの?」と聞くだけでOK。
- 一緒に取り組む必要はなくても、「頑張ってる姿を見るだけ」でも子どもは嬉しい。
④ どうしても続かないときの考え方
やってみたけど続かない…そんなときもあります。
でも、それはツールや本人のやる気のせいだけではないかもしれません。
- やる内容が難しすぎた
- タイミングが合っていなかった
- 生活リズムとぶつかっていた
など、環境との“相性”を見直してみるのも大切です。
ツールを変える、時間帯を変える、声かけの方法を変える。
少しの変化で、また学びが回り始めることも多いです。
⑤ 最後に:学びは一人で進むものじゃない
オンライン学習は「一人で進めるもの」と思われがちですが、
実は「誰かに応援されている」と感じられるかどうかが、大きな差になります。
僕も、たくさんの保護者の方や先生たちと話してきましたが、
子どもたちが伸びる背景には、必ず“見守るまなざし”がありました。
ツールはあくまで道具。
それを使いこなすためには、周囲の理解とサポートが必要です。
6.学びをもっと楽しくするコツと、マインドセットの整え方
これまでは、自宅学習の効率化や継続のコツについてお届けしてきました。
ここでは、「もっと楽しく学ぶには?」「学びへの姿勢をどう育てるか?」というテーマで、
マインドセットの整え方を中心にお話しします。
① 楽しさの源は「好奇心」
「勉強が楽しくない」と感じるとき、
実はその背景に「よくわからない」「関係ないと思っている」という気持ちが潜んでいることが多いです。
つまり、“楽しさ”の入り口は「わかること」「つながること」。
そのためには、興味のあることから始めるのが一番なんです。
- 好きなアニメの制作背景を調べてみる
- 好きなゲームの戦略を数式で考えてみる
- 好きなキャラクターのセリフを英語で訳してみる
このように、「楽しい」と「学び」がつながった瞬間、子どもたちの目が変わります。
② 小さな成功体験を“喜び”に変える
「できた!」という感覚は、学びにおける最大のモチベーションです。
でも、それを感じるには、“ちょっとだけ頑張ればできること”を設定することが大事。
- 5分間集中する
- 単語を3つ覚える
- 一問だけ解いてみる
その達成を一緒に喜ぶことで、子どもは「またやってみよう」と思えるようになります。
楽しいから続く。続くから伸びる。
この好循環の第一歩は、ほんの小さな成功体験から生まれます。
③ 比べるのは“昨日の自分”
「できない」「遅い」と他人と比べると、どうしても自信を失いやすくなります。
そこでおすすめしたいのが、“個人内評価”という視点です。
- 昨日はここでつまずいたけど、今日はできた
- 前回よりも5分早く終わった
- 今回は自分から机に向かえた
こうした「昨日の自分」との比較を習慣にすると、自分の成長が実感できて、学びが“自分事”になります。
これは大人でも大切な考え方ですね。
④ マインドセットを整える「声かけの工夫」
「楽しく学ぶ」ためには、周りの大人の声かけがとても大きな影響を与えます。
NGワード:
- なんでそんなこともわからないの?
- ちゃんとしなさい
- 〇〇くんはもっとできてるよ
OKワード:
- あと少しでできそうだね
- わからないところを一緒に見てみよう
- さっきより集中できてるね
言葉は、環境と同じくらい子どもの意欲に直結します。
「あなたを信じてるよ」というメッセージが込められた声かけは、
それだけで学びを前向きに変えてくれます。
⑤ 学びに“遊び心”をプラスしよう
学び=まじめ、というイメージが強いですが、
実はユーモアや遊び心は学習効果を高めるという研究もあります。
- 勉強中にタイマーでミニゲームをはさむ
- 学んだ内容を家族にクイズで出してみる
- マッチくんのようなキャラと一緒に進めていく
こうした工夫が、「勉強しなきゃ」から「やってみたいかも」に変わるきっかけになります。
“楽しさ”は与えるものではなく、一緒に育てるもの。
最後に:学びを“好きになる”環境を
楽しい学びとは、成績や効率だけでは測れない「気持ちの動き」がともなったものです。
自宅学習でも、学校でも、子どもが「ちょっとやってみようかな」と思えるような
環境や声かけがあるだけで、学びは変わります。
この連載を通して、少しでもヒントが見つかったら嬉しいです。
これからもマッチくんと一緒に、「学びって楽しい」を広げていけたらと思います!
📘 本編はこちらから読めます
家庭学習を「楽しく・続く」に変えるヒントが詰まったシリーズ連載
📎 無料テンプレート配布中
学習記録シートや親子で使えるチェック表など、LINEで配布しています
🔍 Shirutera公式サイトで追加情報をチェック
この記事の補足資料や図解まとめはこちら
📩 LINE登録で、教育テンプレや子育てTipsを毎週お届け!
習慣づくりややる気を引き出すための具体策が詰まっています。