教育・子育ての悩みは、どこに相談すればいいのか分からなくなったときに
【家庭と学びのモヤモヤ】第3回:発達心理×スマホ依存──子どもが“勉強しない”理由を脳から読み解く
2025年6月2日
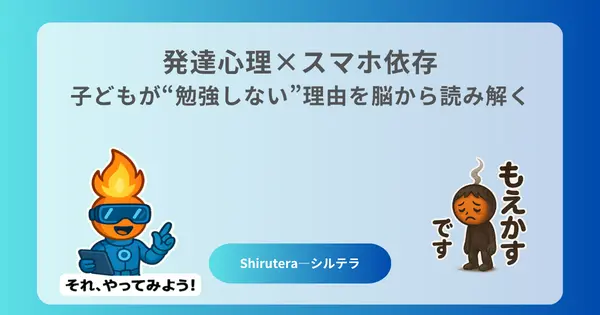
「なんでうちの子、勉強しないの?」
「スマホばかりで、ちっとも勉強しない」
「机に向かっても、すぐに気が散る」
「やる気がないんじゃなくて、そもそも無関心なのでは?」
そんなふうに感じたこと、ありませんか?
子どもが“勉強しない”ように見えるとき、大人は「怠けているのでは」「根気が足りないのでは」とつい考えてしまいがちです。
けれど、その“行動”の裏には、子ども本人ですらうまく言葉にできない感情や困りごとが隠れていることも多いのです。
特に近年は、「スマホの影響で集中できない子が増えている」と言われる一方で、それを一括りに「依存」として捉えてしまうことで、関わり方を見失う大人も増えています。
このnoteでは、「発達心理」と「スマホ依存」、
そして「報酬系(脳の快感回路)」という観点から、
なぜ子どもが勉強を嫌がるのか、そしてどう関わるべきかを解説していきます。
「勉強しない」は“意志の弱さ”ではない
まず、大前提として押さえておきたいのは、
子どもが勉強しない理由は「やる気のなさ」だけでは説明できないということです。
たとえば、以下のような状況に見覚えはありませんか?
- 宿題を始めようとしても、スマホが気になって手が止まる
- 問題集を開いても、数分で席を立ってしまう
- やる気はありそうなのに、なかなか行動に移せない
これらは一見「怠けている」ように見えるかもしれませんが、
実際には“頭が働き出すまでに時間がかかる”“集中を維持するエネルギーが不足している”といった脳の特性が関係していることが多いです。
さらに、「今やりたくない」と感じているとき、
それをうまく言葉にできずに、黙ってやらない選択をしている子どももいます。
それなのに「さっさとやりなさい」と叱られ続けると、
やがて「やる気があっても動けない自分=ダメなやつ」と思い込み、
自己肯定感ごと下がってしまうことも。
子どもが勉強しないとき、まずは「見えている行動の奥に、どんな理由があるのか」を探ってみることが大切です。
スマホ依存と“報酬回路”の関係
ここで少し、脳の仕組みについてお話します。
私たちの脳には、「ドーパミン」という神経伝達物質があります。
これは、何か嬉しいことや達成感を得たときに分泌され、
「もっとやりたい!」「またやろう!」というモチベーションの源になります。
この“ドーパミンが出る仕組み”のことを、報酬系(報酬回路)と呼びます。
そしてスマホには、この報酬回路を強く刺激する要素が満載です。
- SNSの通知がくる
- ゲームでレベルアップする
- ショート動画をスワイプするたびに「次の面白いコンテンツ」が登場する
このように、スマホは「すぐに」「手軽に」「予測できない快感」が得られる設計になっているため、
脳が「これが気持ちいい」と学習してしまうのです。
いわばスマホは、「超高性能なごほうびマシン」。
その一方で、勉強は“ごほうびが遅れてやってくる”タイプの行動です。
- テストの点数が返ってくるのは数日後
- 成績が上がるのは数か月後
- 将来のために必要、と言われてもピンとこない
子どもにとっては、「いま頑張っても報われるのはずっと先」という感覚になるのです。
これは、スマホに慣れた脳にとっては、あまりにも“旨味”がない行動。
そのため、勉強に対するモチベーションは下がりやすく、
逆にスマホのような“即時報酬”にどんどん流れてしまうのです。
“スマホばかり”を叱るより先にすべきこと
ここで注意したいのが、「スマホ=悪」と決めつけないことです。
たとえば、以下のような対応は、子どもとの関係を悪化させる原因になります。
- 無理に取り上げる(反発を招く)
- 「スマホのせいで頭が悪くなった」と責める(自己否定を強化)
- 「昔はゲームなんてなかった」と価値観を押し付ける(時代錯誤)
たしかに、スマホを長時間使いすぎれば悪影響はあります。
でも、本当の問題は「スマホを通して得られる報酬」が
勉強という行動の魅力を上回っているというバランスの問題なんです。
つまり、スマホを制限するより、
「勉強という行動に適度な報酬や意味を持たせる」ことのほうが効果的なのです。
集中力がないのは“発達途中”だから
子どもが勉強に集中できないとき、「集中力がない」「飽きっぽい」といった評価をされることがあります。
でも、これは性格ではなく、“脳の成熟度”の問題かもしれません。
人間の脳には、「前頭前野(ぜんとうぜんや)」と呼ばれる領域があります。
この部分は、感情のコントロール、注意の持続、計画性、判断力、自己抑制といった“高次機能”を司る場所です。
実はこの前頭前野、25歳前後まで発達が続くと言われており、
小学生や中学生の段階では、まだまだ未熟な状態なんです。
つまり、集中が続かない・切り替えが苦手・先延ばしにしてしまう──
こうした行動は、「未熟だからこそ自然な反応」とも言えるのです。
“できない”子ではなく、“まだ整っていない”子
発達心理学では、子どもの行動を「できない=能力がない」と判断するのではなく、
「まだ育ちきっていない=発達の途中」として捉えます。
たとえば、次のような行動も、ただの“だらしなさ”ではないかもしれません。
- 宿題を始めるまでに1時間かかる
- 5分ごとに立ち歩く
- やる気を見せた翌日にすっかり忘れている
これらは、刺激に対する反応の仕方や、注意の維持力の差に由来する行動です。
その背景には、前述の前頭前野の発達だけでなく、個々の特性(脳のタイプ)が大きく関係しています。
ADHDじゃないけど…「グレーゾーン」の子どもたち
最近では、診断はつかないけれど、
- 忘れ物が多い
- 衝動的に話してしまう
- 1つのことに集中できない
──といった傾向を持つ子どもが増えています。
こうした子たちは、「ADHDのグレーゾーン」と呼ばれることもあります。
これは障がいというより、“脳の特徴”として持っている傾向です。
大人にとっては「だらしない」「何度言っても同じ」と感じる行動も、
本人にとっては「気をつけているのに、どうしてもできない」ものかもしれません。
大切なのは、叱ることではなく、“仕組みで支える”ことです。
ADHDじゃないけど…「グレーゾーン」の子どもたち
最近では、診断はつかないけれど、
- 忘れ物が多い
- 衝動的に話してしまう
- 1つのことに集中できない
──といった傾向を持つ子どもが増えています。
こうした子たちは、「ADHDのグレーゾーン」と呼ばれることもあります。
これは障がいというより、“脳の特徴”として持っている傾向です。
大人にとっては「だらしない」「何度言っても同じ」と感じる行動も、
本人にとっては「気をつけているのに、どうしてもできない」ものかもしれません。
大切なのは、叱ることではなく、“仕組みで支える”ことです。
親ができる“やる気の環境づくり”
勉強は、意志だけで続けるには限界があります。
だからこそ、「やる気が出る環境」「取りかかりやすい仕組み」を整えることが大切です。
✔ 小さなごほうびで報酬回路を育てる
報酬回路をうまく使うには、「成功したらうれしい」「頑張ったらいいことがある」と感じられる体験を積み重ねること。
- 問題を1ページ解いたらスタンプ
- 15分集中できたら好きなおやつ
- 終わったら親がリアクション(「すごいね!」)
ごほうびは「物」じゃなくてもOK。
「できた!」という感覚+共感される体験が脳には効きます。
✔ とにかくハードルを下げる
やる気がないとき、「1時間勉強しなさい」と言われても無理です。
でも、「1問だけ」「5分だけ」なら、案外取りかかれるものです。
子どもにとっての最大の敵は「めんどくさい」ではなく、「どうせできない」の無力感。
「自分はやればできるかも」と思える成功体験を小さく積み重ねていくことが、最短ルートです。
✔ スマホとの付き合い方は“制限”より“置き換え”
「勉強中はスマホ禁止」よりも、
「まず5分スマホOK→そのあと10分勉強」という“置き換え型”の導線設計の方が効果的です。
脳は“禁止”より“切り替え”の方がスムーズに反応します。
- 好きな動画1本見たら、1問だけやろう
- ゲームのセーブポイント後に切り替える
- 勉強が終わったら、また続きを見ていいよ
こうした流れを作ることで、報酬回路を敵にせず、味方につけることができます。
「できない自分」ではなく、「工夫すればできる自分」へ
子どもにとって一番つらいのは、「やる気が出ない」ことより、
「やろうとしてもできない自分を責められること」です。
- 怒られたからやる
- 諦められているからやらない
- 自分には無理だから向いてない
──そんなふうに思い込んでしまう前に、
「どうすればやりやすくなるか」を一緒に考えてくれる大人の存在が、何よりの支えになります。
【まとめ】理解から始める「学びの再設計」
子どもが“勉強しない”のではありません。
今の脳では、“まだ難しい”だけなのです。
- ドーパミンに支配されたスマホの誘惑
- 発達途中で未熟な前頭前野
- 個性としての集中力のばらつき
- 自信がないから動けない心理的ブレーキ
これらすべてを、「努力不足」や「育て方の問題」として片づけてはいけません。
大人が脳と心理の仕組みを理解し、
子どもに合った“仕組みと習慣”を整えていくことで、
学びに向かうエネルギーは確実に回復していきます。
▶ Shiruteraの連載まとめはこちら!
このnoteは、「Shirutera」で展開している【学びの悩み×心理】シリーズの1本です。
他にも、以下のようなテーマを扱う記事を順次公開しています:
- 不登校×発達心理:「行けない子」とどう向き合うか
- やる気×教育心理:「続かない子」に必要な関わりとは?
- スマホ依存×親子関係:禁止より“習慣化”の考え方
- 自宅学習×集中力:グレーゾーンの子どもへの実践例
勉強が嫌いなのではなく、
「どうすればうまくやれるか」がまだ分かっていないだけ。
その“答えを一緒に探してくれる大人”がそばにいれば、
子どもはきっと変わっていきます。
学びを支えるのは、叱責でも評価でもなく、理解と仕組み。
今日からできる小さな工夫を、ぜひ始めてみてください。
📘 本編はこちらから読めます
教育とAIのリアルを描いたフィクション連載
📚 無料テンプレート配布中
LINEで配信している限定テンプレート・PDFはこちらから
🌐 Shirutera公式サイト
脳科学・教育心理・行動科学をもとにした「学びと子育ての本質メディア」
📩 LINE登録で、教育テンプレや子育てTipsを毎週お届け!
習慣づくりややる気を引き出すための具体策が詰まっています。