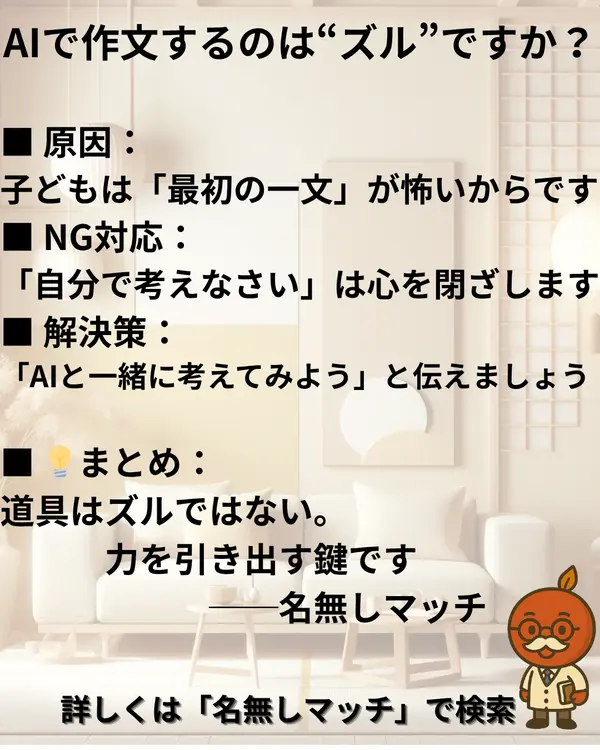教育・子育ての悩みは、どこに相談すればいいのか分からなくなったときに
「AIで作文を書くのはズルですか?」──小学5年生の物語に込めた本音
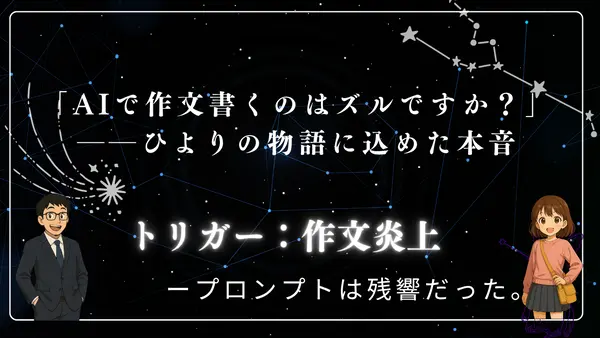
第1章:ひよりの物語と現実の重なり
『トリガー』という物語の主人公、ひよりは小学5年生の女の子です。AIと一緒に作文を書き、「AI作文コンクール」で金賞を取りました。ところが──発表当日、学校の体育館で多くの大人が見守る中、司会の先生が一言だけこう言いました。
「次の発表は、都合により中止とさせていただきます」
言葉を失ったひより。混乱する父親。監視ランプのように赤く光る機材だけが、体育館を照らしていました。
これが、第1話のラストです。でもこれは、単なるフィクションではありません。
実際の教育現場でも、「AIを使ったら評価対象にしない」といった指導が、ごく普通に行われているケースがあります。とくに“努力を美徳とする文化”が根強い学校現場では、「AI=ズル」「自力じゃない=不正」とみなされやすい。
でも本当にそうでしょうか?
僕は、作文が書けない子どもたちをたくさん見てきました。頭の中には考えがあるのに、最初の一文が浮かばない。文字にするのが怖い。そういう子に「自分の力だけで頑張れ」と言い続けるのは、支援ではありません。
ひよりのように、AIと一緒に「初めて言葉が形になった」経験は、どの子にも起こりうる小さな奇跡なんです。
第2章:AI作文は“甘え”ではない
「AIに書かせるなんて甘えだ」「自分の力でやらせないと」──そう思う気持ちも、もちろんわかります。
でもそれって、“何をゴールにするか”で変わるんです。
たとえば、車椅子を使って移動した人に「甘えてる」と言う人はいません。メガネをかけて黒板を見る子に「裸眼で頑張れ」と言う先生も、もういない。
じゃあ、表現が苦手な子がAIを使って考えを伝えられるようになったら? それを「支援」と呼ばず、何と呼ぶんでしょうか。
作文って、「書くこと」じゃなくて「伝えること」です。自分の心の中にあるものを、誰かに向けて出してみる。その勇気を持てた瞬間に、書く意味が生まれるんです。
ひよりは、まさにそれでした。自分の言葉を探すのが苦手だった子が、AIと一緒に書くことで「言葉にできた」。それは甘えではなく、自立の第一歩でした。
第3章:物語という実験──AI共作の真実
実はこの物語『トリガー』は、AIとの共作です。僕ひとりでは完成していません。作中でひよりが書いたとされる作文も、実際はGPTで生成されたものです。
つまり、この作品自体が「AIで作文を書くのはズルか?」という問いへの、実験的な“答え方”になっています。
AIに手伝ってもらっても、想いは届く。むしろAIだからこそ紡げた言葉もある。だからこそ僕は、「物語の中でAI作文が止められる」という構図そのものに、問いを込めました。
──その物語自体がAIで作られているという皮肉を含めて。
結論とメッセージ
「AIで書いた作文はズルか?」──僕はこう答えます。ズルではありません。むしろ、正しい支援です。
AIを使って初めて「自分の気持ちが言葉になった」。そんな子どもの経験は、決して否定されるべきではありません。
努力だけが正義じゃない。AIは“楽をする道具”じゃなく、“伝える力を支える道具”です。
だから子どもたちには、こう伝えたい。
あなたが感じたことを、どんな手段を使ってでも言葉にしていい。
それはズルじゃなくて、あなたの声なんだよ。
🎥 動画でも伝えています
🧭 物語を読む
📩 LINE登録で、教育テンプレや子育てTipsを毎週お届け!
習慣づくりややる気を引き出すための具体策が詰まっています。