教育・子育ての悩みは、どこに相談すればいいのか分からなくなったときに
【相互リンク企画】金賞を目指すか、楽しさを大切にするか──部活動の目標をどう決める?
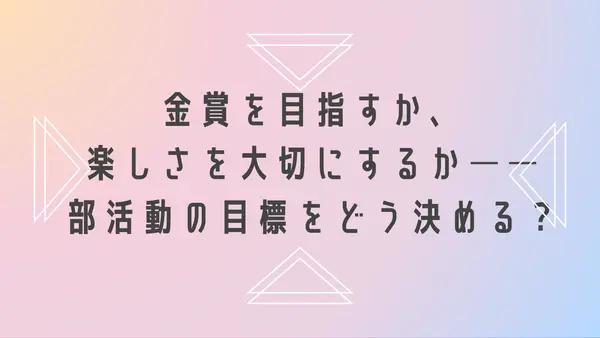
子どもの「学びの悩み」を心理から解決──発達・教育心理の実践知をまとめて紹介
今回は、X(旧Twitter)を通じてご縁があったしんや先生と、note相互リンク企画をさせていただきました。
教育・指導の現場に関わる者同士、お互いのnoteを読み合い、その魅力を紹介し合う試みです。
ぜひ、この機会に「自分と違う視点」にふれていただけたら嬉しいです。
僕が今回ご紹介するのは、こちらの記事です👇
🎼 吹奏楽部の目標、金賞か楽しさか──その先にある本当の宝物
💡 記事紹介
しんや先生は、元・中学校音楽科教員としてのご経験をもとに、部活動指導にまつわる“本質的な問い”を投げかけてくれています。
「金賞を取るべきか?楽しさを重視すべきか?」
──この“よくある対立”に、真っ正面から向き合う記事。でも、結論はどちらかに偏るものではありません。
「誰が、どうやって、その目標を決めたのか?」
という問いの重みが、記事の中心にあります。
結果を出す過程で生まれる絆。楽しさを積み重ねていく中で芽生える主体性。
どちらも“正解”になりうるからこそ、「誰も置き去りにしない環境づくり」が大切なのだと──。
「指導者は“決める”のではなく、“聴く”ことが仕事である」
という一文に、僕自身も強く共感しました。
★ 追加感想
しんや先生がたくさん書いてくださったので、追記します。
吹奏楽部の目標について、「金賞か楽しさか」という問いかけに対して、どちらかに決めつけるのではなく、その過程をどう築くかという“プロセス”の重要性にフォーカスされていた点がとても心に残りました。
どちらの目標にも価値があることを丁寧に認めたうえで、「誰がどう決めたか」を大事にする視点は、教育や指導に関わる多くの人にとって、大切なヒントになると感じました。
とくに、中学校の部活動では、様々な思いを持つ生徒たちが一つのチームとして活動することが多い中で、目標設定のプロセスこそが、その後の充実度や満足感に大きく影響するというご指摘に深く納得しました。
「コンクールで勝ちたい」という気持ちも、「楽しく音楽と向き合いたい」という気持ちも、どちらも本物で、どちらかが間違っているわけではない。
けれど、どちらかの気持ちが軽視されたままチームが進んでしまうと、心のどこかで置いてけぼりになる生徒が出てしまう──そんな現実に、指導者として何度も向き合ってきたという経験が言葉の随所ににじんでいて、とても信頼できる記事だと感じました。
生徒たちが「自分たちで考えて決めた」という実感を持ちながら進める環境をつくること。
これは吹奏楽に限らず、学校教育や家庭教育にも通じる普遍的なテーマだと思います。
記事の最後で語られていた「引退の日に、どんな顔で振り返るか」という視点──これはまさに、生徒の人生の中で部活動がどんな意味を持つのかを問い直す、素敵な問いかけでした。
どちらが正しいかではなく、どのようにその道を選ぶか。
その価値を、改めて考えさせてくれる記事でした。
🔁 こちらの記事もぜひご覧ください!
今回、しんや先生にも僕のnoteを読んでいただき、紹介していただいています👇
子どもの成績や成長をどう捉えるか──というテーマで、むすこの実体験をもとに綴った記事です。
「家庭での関わり」「ご褒美との向き合い方」など、保護者・教育者どちらにもヒントになる視点を詰め込みました。
紹介記事も書いてくださりました。ありがとうございます。
これからもたくさんの人とつながっていきたいです。
よろしくお願いします。
しんや先生、ありがとうございました。
✅ おわりに ──相互リンク企画にご興味ある方へ
今回は、しんや先生とのご縁から「note読みあい企画(相互紹介)」を試験的にスタートしてみました。
ありがたいことに、読者の方からも好反応をいただいています。
今後も、教育・子育て・心理・学びに関心のある方と、
お互いの記事を読み合い、広げ合う企画として続けていきたいと考えています。
「ぜひ読んでみてほしい記事がある」
「一緒に発信を盛り上げたい」
という方は、ぜひお気軽にご連絡ください。
ご連絡は下の公式LINEか、XのDMまでお願いします。
XのDMは返答までお時間をいただく場合があります。ご了承ください。
📣 ほかの活動や更新情報はこちらから
📩 LINE登録で、教育テンプレや子育てTipsを毎週お届け!
習慣づくりややる気を引き出すための具体策が詰まっています。