教育・子育ての悩みは、どこに相談すればいいのか分からなくなったときに
子育てしながらAI自動化に挑む──LINEカスタマーBot開発記から学んだ「仕組み化」の可能性
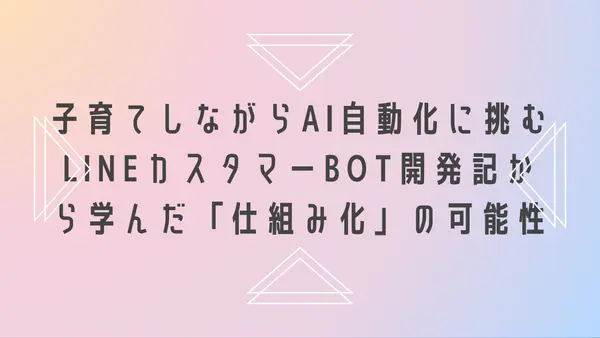
子どもの「学びの悩み」を心理から解決──発達・教育心理の実践知をまとめて紹介
最近、「子育てをしながら、自分のペースで新しいことに挑戦している人」のnoteに出会うことが増えてきました。そんな中で目に留まったのが、ノブキ(@noble_hare5414)さんのnoteでした。
タイトルは「子育てしながら178時間でLINE AIカスタマーサポートをAI駆動で作った話」。この時点で、すでに興味を引かれました。子育てと並行して何かを「作る」というだけでも相当大変なことなのに、その取り組みに178時間を費やしたという事実にまず驚きました。
読み進めてみると、派手な言葉で飾るわけでもなく、淡々と、しかし丁寧にその過程が綴られていました。育児中の生活リズムの中で、自分のやりたいことと向き合いながら、時間を積み重ねていく。その姿に強く共感しました。
とくに印象に残ったのは、「気軽な挑戦として始めたことが、やがて自分の中で意味を持ちはじめ、深めていった」という感覚です。子どもが小さいと、自分のことを後回しにしがちですが、ノブキさんはその日常の中で「できる範囲で動いてみる」という柔軟なスタンスを持ち続けていたように思います。
技術的な内容についての詳しい記述もありましたが、何よりもその工程に取り組む「姿勢」が、一番の読みどころでした。どんなに専門的な技術があったとしても、「やってみよう」と思えなければ前に進めない。その“最初の一歩”に誠実に向き合う姿が、読み手に安心感を与えてくれます。
このnoteを読んで、「子育て中だからできない」ではなく、「子育て中でも、少しずつでも、動いていいんだ」と思わせてくれました。特別な人だからできたのではなく、自分なりのやり方で続けてきたその日々こそが、何よりも尊いものだと思います。
ここからは、そのnoteを読んだあとに自分の中に生まれた変化について、少し振り返ってみたいと思います。
まず、最初に出てきたのは「自分にもできるかもしれない」という感覚です。普段なら「無理だ」と決めつけてしまうようなことでも、「できることから始めてみる」という視点に変えるだけで、ずいぶん心が軽くなると気づきました。特に子育て中の人間にとっては、「完璧にやること」よりも「今の自分でやれることを選ぶこと」のほうが、よほど現実的で力強い。
また、ノブキさんのnoteには「自己肯定感の再構築」につながるヒントもたくさんありました。誰かに評価されるためではなく、自分自身が「やってよかった」と思えるプロセスこそが、結果よりも大事なのではないか。その視点は、僕自身の発信や行動にも大きな影響を与えました。
僕はこれまで、「価値がある」と思える内容しか発信しちゃいけない気がして、アウトプットをためらうことがよくありました。でも、ノブキさんのように「やってみた」「作ってみた」「動いてみた」と記録することが、同じような境遇の誰かにとっての励みになるのかもしれない。そう思えるようになっただけでも、大きな変化だったと思います。
noteという場所は、誰かの記録や気づきが、そっと他の誰かを支えることができる空間です。ノブキさんのnoteは、まさにそんな「そっと支えてくれる記録」でした。
だからこそ、僕もまた、自分なりのペースで、今の立ち位置から書いていこうと思います。この記事も、そんな思いから綴ったもののひとつです。
なお、僕自身も教員として、子育てと向き合いながら「仕組み化」や「自動化」に挑戦しています。
以下の記事では、「自分にできる範囲でやってみた」取り組みの記録として、試行錯誤をまとめています👇
📘 SFマッチ名義の記事(副業×自動化×教育)
👉 記事はこちら
興味を持ってくださった方がいれば、こちらものぞいてみてください。
きっと、どこかに「自分のやり方で進んでいいんだ」と思えるヒントがあるはずです。
📩 LINE登録で、教育テンプレや子育てTipsを毎週お届け!
習慣づくりややる気を引き出すための具体策が詰まっています。