教育・子育ての悩みは、どこに相談すればいいのか分からなくなったときに
子どもと向き合ってもうまく話せない──“歩きながら”が会話を変える理由
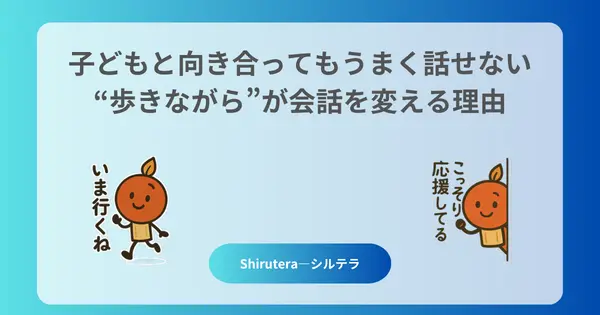
──このひと言、どれくらいの親が跳ね返されたことがあるだろう。
「べつに」
「ふつう」
「なんもない」
そんな短い返事に、ちょっと寂しくなったり、イラッとしたり。
“ちゃんと話してほしい”って思ってるのに、なんだか会話にならない。
でも最近、ふと思った。
もしかして、向き合いすぎてたのかもしれない。
目と目を合わせて、言葉で引き出そうとするほど、
子どもは黙り込む。
なぜか話題が終わる。
空気が重くなる。
それが、
「歩いてたとき」や
「並んで座ってるとき」だと、
急にぽつぽつ話し出すことがある。
今回のnoteでは、そんな「向き合わないことで心が近づく」という
ちょっと不思議で、でも確かに効果のある会話のコツを紹介していきます。
キーワードは、
“横並び”と“歩きながら”。
心理学や親子関係の研究もまじえながら、
「どうすればもっと自然に子どもと話せるのか?」を一緒に探ってみましょう。
🧠 第1章:「向き合う」と話せなくなる理由
親としては、ちゃんと目を見て話したい。
「あなたのこと、ちゃんと大事に思ってるよ」って伝えたい。
でも、子どもにとってはそれが逆に“プレッシャー”になることもあります。
心理学では、「視線の圧」という言葉があります。
これは、人と視線を合わせることで感じる“緊張”や“不安”のこと。
とくに子どもはまだ言葉で感情を整理するのが難しいぶん、
視線や表情から「読み取られすぎる」のがこわいと感じることがあるんです。
たとえば、
「なにか隠してるな」って思って、じっと見つめて問いかけると、
子どもは“見抜かれた”と思って防御反応をとる。
黙る
話をそらす
「べつに」と言う
これは、相手に反抗してるのではなく、
自分の気持ちを整理できていない状態で“言語化を求められた”からなんです。
つまり、
「ちゃんと話してほしい」からこそ、
親がつい向き合ってしまうけれど──
それが子どもにとっては“壁”になることもある。
じゃあ、どうしたらいいのか?
それが次の章で紹介する、“横並び”の魔法です。
🤝 第2章:「横並び」がもたらす心理的安全性
“対面”では話せないのに、“横並び”だと話せる。
そんな経験、ありませんか?
実はこれ、ただの偶然ではありません。
心理学の研究でも、「会話の姿勢(ポジショニング)」が心の開き方に大きく影響することがわかってきています。
📘 横並び=“視線の圧”が減る
人と人が会話をするとき、
正面に座ると、どうしても「視線」や「表情」を強く意識します。
それが親子だと特に──
「ちゃんと聞かなきゃ」
「ちゃんと答えなきゃ」
という空気が強くなる。
一方、横に並んで歩いたり座ったりすると、
お互いの視線がずれて、空気が“ゆるむ”。
しかも“横並び”は、心理的に「対等感」が生まれやすい配置。
「上から見下ろされる」でもなく、
「目を見て詰め寄られる」でもなく、
ちょっとだけ心の壁をゆるめてくれるポジションなんです。
💡 実験でも裏づけあり
実際、子どものカウンセリングなどでも
“対面ではなく斜め横”の配置を取るケースが多くあります。
アメリカの発達心理学者トーマス・ゴードンは、
「真横に並ぶと“共感的な関係性”が築きやすくなる」と述べています。
🏃♂️ “歩きながら”だと、もっと話しやすくなる理由
さらに、歩いているときには
✅ 目を合わせなくてすむ
✅ 沈黙しても気まずくない
✅ 周囲の風景が“話題”になってくれる
といった効果があるので、
会話のハードルが自然と下がります。
親としては「ちゃんと座って話す方がいい」と思いがちですが、
子どもにとっては、「歩きながら」や「横で作業しながら」の方が
ずっと“自分の言葉”が出しやすくなるんです。
次の章では、そんな“横並びコミュニケーション”を
実際にどう活用すればいいのか、
おすすめのシーンと親の対応のコツを紹介していきます。
🚶♀️ 第3章:おすすめシーン3選と親の反応のコツ
「横並びで歩きながら」が良いとわかっても、
実際にいつ・どうやって取り入れたらいいか分からない──
そんな方のために、今日から使える“おすすめシーン”を3つご紹介します。
✅ シーン①:買い物の帰り道
買い物袋を下げながら、
信号を待つとき、歩道を並んで歩くとき。
この“なんでもない時間”が、
子どもにとっては話しやすいスキマになります。
会話を目的にしないぶん、構えず自然に話しやすいんです。
✅ シーン②:車の助手席にいるとき
送迎や買い物、ちょっとしたドライブのとき。
真正面じゃなく、斜め前にいる状況は、
「目を合わせすぎない安心感」があります。
しかも車内は音が少ない分、言葉の間も心地いい。
✅ シーン③:なにか作業をしているとき
一緒に洗い物をする
勉強の準備をする
散らかしたおもちゃを片づける
この「横に並んで、手だけ動かしてる時間」って、
実は“気持ちがこぼれやすい”時間なんです。
💬 会話のコツは「聞こうとしすぎない」こと
子どもが話してくれるとき、
つい「深掘り」したくなる気持ち、ありますよね。
でもそれが、“また聞かれる”というプレッシャーになることも。
ポイントは:
・「そうなんだ〜」と流してみる
・「うんうん」だけでも十分
・聞かれてもすぐ答えず、「どう思ったの?」と返してみる
話すより、「その話をしてもいい空気」を出すほうが、
子どもにとってはずっとありがたいことなんです。
🔚 おわりに:会話は、向き合わなくてもできる
子どもが話してくれないとき、
「どうすれば聞き出せるか?」を考えがちだけど、
ほんとは“聞き出す”必要なんてないのかもしれません。
ただ一緒に歩く。
同じ方向を見て過ごす。
それだけで、子どもの心は少しずつほぐれていく。
完璧な会話じゃなくていい。
気の利いた返しも、深掘り質問もいらない。
大事なのは、“話しても大丈夫な空気”をつくること。
向き合いすぎず、並んで歩く。
それだけで、ふっと心が動き出す瞬間があります。
📘 関連情報と無料テンプレートのご案内
本記事で紹介したような「親子の心が近づく工夫」や「家庭で使える行動心理のTips」は、
教育×心理メディア「シルテラ|SHIRUTERA」にて、すべて無料で公開中です。
📥 今すぐ試せる無料テンプレート付き特典も!
LINE登録で受け取れます👇
https://lin.ee/7teX4nMG
📩 LINE登録で、教育テンプレや子育てTipsを毎週お届け!
習慣づくりややる気を引き出すための具体策が詰まっています。